乾かしてください。
一
殴った拳にじいぃんと響く鈍い痛みを感じながら、ふとこのふざけた提案は良いかもしれないと思い至る。
口にした時は単なる冗談だったが、よくよく考えれば今の状況に丁度良い抑止力になるかもしれない。
少し・・・いや大分、非人道的かもしれないが。
思い出しのは今朝のことだ。
うたた寝した身を寝かせてくれたまでは良かったが、その横で一緒に寝るという図々しさ、加えて寝ぼけてしがみついてくるような相手だ。
いつまでとはハッキリ言えなくてもしばらく置くことを決めたからには、どこで寝るということからその他もろもろ、ある程度のルールを作らねばならない。
間違っても、寝ぼけてうっかりいたしてしまった、なんてことになるのはごめんだ。
「奉仕は、いらないわ」
「!!」
「その代わり、ペットならペットらしく飼い主の言うことをよく聞いて、言い付けは守ること」
紫色の瞳がパチリと瞬きをする。
「分かった、飼い主の言い付けは守る」
深く悩むこともなく、瞬き一回で了承される。
本当にそれで良いのかと聞きたいくらいには早い返答だったが、それならそれで有り難い。
今後、詳しくルールを決めていこうと考えながら、取り合えずはそこまでにして。
「風呂、入ってきなさいよ」
「・・・良いけど、あんたは?」
「は?私はもう入ったわ」
買ってきたばかりの紙袋から着替えを取り出す相手にバスタオルを渡す。
受け取る手が、するっと甲を撫でていく。
「っ!?」
「何だ、風呂に入れて洗ってくれんのかと思った」
本当にこいつは口が減らない。
あまりにも馬鹿馬鹿しすぎてルールにわざわざ、風呂は一人で入ること、なんて書く気にもならない。
「・・・ユーリ、夕飯抜きね」
言い捨てて背を向ける。
「・・・ごめんなさい、もーしません」
まるで棒読みな謝罪に溜息が漏れたのは仕方が無いだろう。
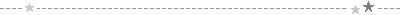
管理人の窓口を閉める時間までまだもう少しある。
坐り心地の良い管理人の椅子に座って、ボールペン片手に肘をついて片頬を乗せる。
真新しいノートをめくった最初の一ページ目。
ペットの心得として、衣食住を飼い主が全て賄う代わりに、飼い主の言い付けを必ず守ること、と書き出した。
その下に細かいルールを書き出そうとして、さて何から書こうと悩む。
「・・・・・」
思いついてサラサラとペンを動かす。
多少筆圧が上がってしまったのは致し方ないだろう。
1行目に書かれた言葉は、「セクハラ禁止」だった。
書いてて早々にアホらしくなってきた。
残りは、気が付いた時に足していこう。
ペンを手から離して、背もたれに沿ってうーんと大きく伸びをした。
ポタリ。
仰向いた額に何かが垂れてくる。
目を瞑ったのも確かだか何だか暗いと思えば、開いた視界に覗き込むようにしてユーリが立っていた。
「何してんだ?」
伸びをした姿勢のまま瞬きしながら見上げていれば、またポタリと落ちてくる、水滴。
「水もしたたるイイオニーサン。たれてるんですけど」
額に落ちた水滴を袖口で拭おうとすれば、それより早く悪い悪いと言った相手のその頭にひっ被せられていたタオルの端で拭われた。
一瞬、タオルで視界が遮られて、シャンプーの香りとそれとはまた別の香りに包まれる。
それが何なのか分かってすぐに、顔に血の気が上った。
「・・・・なんだ、怒ってんの?」
タオルが退けられた後にまた覗き込んできた顔が、こちらを見て不思議そうに聞いてくる。
この男・・いやペット、湯上りで色気具合が上がっている。
無理だ、勘弁して欲しい。
「・・・床が水浸しにならないように、ちゃんと乾かしてから出てきなさい」
何とか、そういうのが精一杯。
彼氏と別れて間もないからって、若い年下に飢えてどうする。
目を覚ませ、自分。
こっちの言葉にどこか釈然としない様子で、でもユーリは洗面所の方へ歩いていった。
思わず、盛大な溜息を吐いてしまった。
異性の匂いで顔を赤らめるって、どんだけ初心か、もしくはどんだけ欲求不満なんだ。
「コーヒーでも飲もう」
時刻はやっと七時を回った。
管理人業務は終了した旨を表す札を出し、ガラス窓に鍵をかける。
書きかけのノートは閉じて小部屋の電気を消した。
苦い苦いブラックが飲みたい。
切実にそう思った。
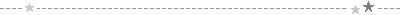
フオーッというドライヤーの音が響いている。
あの長さは乾かすのも大変そうだなと思っていれば、カチッとスイッチを切る音がして、その音は思いのほか早く途切れた。
不審に思いながらコーヒーの準備をしつつお湯が沸くのを待っていれば、肩にタオルを垂らした臙脂色のジャージ姿の相手が洗面所から出てきた。
つまりは、生乾きということだ。
「・・ユーリ」
仕方が無いのでちょいちょいと手で呼び寄せれば、ペタペタと裸足で歩いてきた。
そういえばスリッパが一足しかない。
素足にフローリングは冷たいだろう、今度買ってくるかと脳内で買い物リストに付け加える。
「お湯沸いてるぞ」
よそ見している間に沸いていたらしい、火を止めてやかんをミトンで掴んで中身をポットに移す。
用意していたドリップコーヒーに注いで、隣のカップには直接注いで渡す。
受け取った中身を覗いてスンスンと匂いを嗅ぐさまは、まさに犬みたいだった。
「ココア」
言えば、嬉しそうな顔で飲み始めるその背を押してテーブルにつかせた。
無頓着なのはらしいといえばらしいが、それでこの髪質だというのなら羨ましさを通り越して憎たらしくもある。
洗面所から持ってきたドライヤーをセットしてスイッチを入れれば、大人しく席についてココアを飲んでいた相手は驚いた顔をした。
何も言わないので、勝手に乾かし始める。
すでに乾きかけていた頭頂部はサラサラだ。
「自然乾燥してたら髪が痛むよ」
「・・・面倒くさくてつい、な」
まあそうだろう、この長さだ。
じゃあ切ればいいじゃないかとも思うが、それも何だか勿体無い。
上から丁寧にほぐすようにして温風を当てていく。
指の間を通り過ぎる髪が、柔らかくて気持ちがいい。
ついつい夢中になって手櫛で梳き続けていれば、居心地悪そうに身じろぎをされた。
「あ、ごめん。嫌だったかな」
もうすっかり乾いた髪には羨ましいほど、キューティクルが輝いている。
最後にブラシで梳いておこうかと思ったが、嫌ならやめておこう。
そう思って離そうとした手が掴まれた。
「嫌じゃ、無かった」
「・・そか、なら良かった」
ほっとしていれば手がくいっと引っ張られる。
はっとした時には、手の平にするすると擦り寄られた。
「ありがとう、な」
しまった。
湯上りフェロモンがまだ出されていた・・・!
何とかもう一方の手を伸ばして、自分で整えたばかりの美しい毛並みをわしゃわしゃとかき混ぜる。
「うわ、ちょ・・やめろっ」
ぐしゃっとなってしまったのは勿体無かったが、その様に平常心と手を何とか取り戻せてほっとした。
◆アトガキ
2013.12.09
キミペってどういうルールにしてたんだっけと思い出そうとして思い出せず。
取り合えず、抱きついたり過度なスキンシップは禁止にしてたような気もする。
後は、お風呂で頭洗ってあげてたのは覚えてるんですが・・・。
漫画を持っているわけでも無いから調べようが無いので、もうこのままうろ覚えで突き進む予定です。
icon by Blancma
background & line by web*citron