飼ってください。
一
「あなたの事情は分かった」
「・・・・・」
「少しの間というのは、どのくらい?」
「!!いいのか?」
「どのくらい?」
「・・・・国の知り合いに連絡とって、代わりの資金なり帰りのチケットなり・・」
「知人の救助、もしくは救援物資が届くまでってことね?」
「・・・そーなるな」
そろそろ管理人窓口を開けなければならない。
何だかんだあったことで、空ける前にやってしまおうとおもっていたあれこれは、何もできていない。
ゴミ回収の部屋を整理すること、玄関前の掃除、荷物を受け取り忘れていそうな住人への連絡、など等。
そのことを告げれば、即答で「手伝う」と帰ってきた。
もちろん、お願いするつもりだ。
さて、暫くの間と言うが、それはどのくらいになるだろう。
まずは、その救助要請をして・・・・どうやって救助要請をしたのだろう?
「・・・・メール?電話?」
「・・・メールで。パソコン、借りれるか?」
思ったとおり、まだ何の連絡も出来ていなかった。
危うく、来もしない救助を待ってしまうところだった。
「言ってくれれば、いつでも貸すから」
「助かる。ありがとな」
引越しでも勿論持ってきた相棒のようなノートPCをダイニングテーブルに置いて、コードをつなぐ。
そこまでやってから、あ、と声を上げた。
「ん?どうかしたか」
「ごめん。まだネットに繋げないわ」
どういうことだと首を傾げる相手に、自分もまだここに引っ越してきたばかりで、身辺が整っていないのだと伝える。
「へえ・・どーりで、随分ものが少ねえなと思ってた」
「そういうわけだから、もう少し待って」
「ああ、いつでもいいぜ」
いつでもいいって、のんきなものだと思うけれど、取り合えずネットの契約をして早めに繋げられるようにしなければと思う。
携帯のメールも考えたけれど、この携帯で送れば送信元は自分になってしまう。
見ず知らずからの相手から届いたメールなんて、いまどき誰も開かないだろう。
ウイルスか架空請求か。
何にせよ、疑われてゴミ箱に捨てられるのがオチだ。
きょろきょろと改めて部屋の中を眺めている相手を横目で見て、小さく溜息を吐いた。
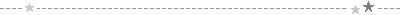
「じゃあ、これでアパート前の掃除をお願い」
「おう」
箒とちりとりを渡して見送ってから、窓口の椅子に座る。
まだ読み込めていない注意事項が書かれたノートを眺める。
前任者であったいとこは、ちょっとばかり破天荒な性格ではあるが意外と几帳面だった。
後に、私が来るということは知らなかっただろうけれど、誰が来てもいいようにと連絡ノートを残していってくれていた。
綺麗に整頓された数冊ある内の一冊に目を通す。
2階の4号室のおじさんはいつも玄関のポストを見忘れるから、ある程度溜まってしまったら部屋の扉についているポストに届けてあげた方がいい、とか3階と4階に住んでいる小学生の男子と女子は同じ小学校で、時々ふざけて屋上やら駐輪場に隠れたり物を隠していたりするから注意、とか。
他にも誰それは耳が遠いからとか電話ではなく何か伝えるなら直接とか、好意で煮物をくれるけれどたまに不思議な味があるぞ!とか。
覚えておかないといけないことと、彼個人の人間観察日記かと思うような一口メモがいっぱい。
来たばかりなのに、読めば少しその住人の人となりを知ることが出来て、とても助かる。
それに何より驚いたことは、いとこの文字から伝わること。
「・・・・不思議な味って何だろう」
どの人も、すごく人間味があって暖かくなる。
実際に会ってみないと確実なことは分からないけれど、悪い人や怖い人は一人もいなさそうでほっとする。
ちゃんとここで管理人していたんだなあと、今はどこか異国の空の下にいるはずのいとこのことを思い浮かべた。
「・・、おいって」
「あ!ごめん・・なに?」
外から窓を叩かれていたことに気が付かなかった。
管理人失格だ。
慌ててガラス窓を開いて顔を出す。
「いや、掃除終わったって伝えようと思って」
「ありがと、う・・・」
「?」
言ってから、しわがあるけどそれなりに綺麗だったシャツが汚れてしまっていることに気が付く。
そういえば昨日からずっとこの服を着ているはずだ。
下着も昨日からそのまま?
思い浮かべて、ちょっと赤くなった顔をそらしてぐるぐると考える。
商店街にどこか服を揃えるのに良さそうな店はあっただろうか。
いや、それだったらついでに、いつまでいるんだか分からないユーリの分の日用品も揃えてしまいたい。
そう考えると、この駅ではなく隣駅の駅ビルに行ってしまった方が良さそうだ。
良さそうだが、今は手が離せない。
夜まで待ってもらうか。
・・・いいや。
「何か、顔赤くねえか?」
「いや、大丈夫。その箒とちりとりは倉庫にしまって、そしたら買い物に行っておいで」
「大丈夫ならいいけど・・・買い物?」
「服と、必要なものを買っておいで。お金は後で返してくれれば良いから」
言えば、びっくりしたように目を見張られる。
そして次の瞬間、眉根を寄せられた。
怒ったようなその顔がぐっと近付いて、何だと少し背もたれに身体を寄せる。
「」
「え・・何、どうしたの」
「昨日会ったばかりの素性が知れない相手に、金を渡すのか?」
「いや、まあ持っていかれちゃったら仕方が無いなと思うけど」
「そんなだと、いつか有り金全部ぶんどられるぞ」
「そこまで抜けてないつもりなんだけど」
「・・・つもり?あのなぁ、俺が言うのもなんだけど・・あんた昨日から・・」
何故、自分が怒られなければならないのだろう。
窓口を挟んで、腰に手を当てたユーリにこんこんと説教を受けている。
「・・・じゃあ、ユーリは金持っていなくなるわけ?」
むっとして、その話を遮って問う。
さすがに私だって、誰彼構わず援助してあげるほど偽善者ではない。
今この場において、対象者はユーリであってその他大勢は関係が無い。
そう告げれば、相手の口は閉ざされる。
「どうなの?」
「・・・・ね-よ」
「?・・聞こえないんだけど」
「んなことしないって言ったんだ」
「・・・じゃあ、問題ないじゃない」
さらっと告げて、このお話はもうお仕舞いと締める。
何か言いたそうにした相手は、ぐっと片手を握って・・・そして溜息を吐いて脱力した。
「・・・一緒には行けねーの?」
「だって、まだここにいないとならないもの。何で?」
「いや。・・・この辺よく知らねえし」
「ああ、そうよね」
確かにと頷く。
それじゃあ日用品はもう少し後回しにしても、衣服だけでもと商店街の店の並びを思い出す。
取り合えず手を洗って待っててと告げて、メモ紙に商店街の道を書く。
まるではじめてのおつかい、みたいだ。
思いながらおかしくてふふっと笑う。
服が置いてそうだった辺りに丸をつけてから、お財布を開けてからいくつかお札を取り出しかけて、その手を止める。
迷ったのは一瞬で、1枚だけ取り出して財布を仕舞う。
そのままむき出しじゃあ余りにもと、悩んだ末に化粧品を入れていた小さいポーチにそのお札をしまった。
「はい」
「・・・・俺に、これを持てって?」
渡された花柄のポーチに、口元がぴくりと引きつっている。
やっぱり、男性にこの柄は無かったかと、他に何かあったかなと目をうろつかせる。
「あー、いいよ、このまんまで」
「え、でも」
「行きだけだし。帰りは買ったもんと一緒に袋にでも入れちまえばいいし」
「・・そう」
「ありがとな。んじゃ、ちょっと行ってくるわ」
「気をつけて、いってらっしゃい」
ひらひらと手を振る相手を、窓口からぼけっと見送る。
もしかしたら。
もしかしたら、これでお別れになるかもしれないなと、頭の隅っこで考えておく。
そんなことしそうに無いと思っても、昨日今日の彼しか知らない。
もし万が一のことがあっても、傷がつかないように。
遠ざかる背中を見て視線をそらした。
心にそっと防御線を張った。
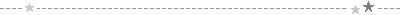
「ただいまー!」
「ただいまっ!」
「おかえりなさい」
元気よく帰ってくる小学生の二人に、笑顔で返す。
時刻は夕暮れの少し手前。
この二人が、時々いたずらっ子と化す二人かと顔を記憶する。
仲良く階段を登っていく姿を見送って、知らず溜息を吐いた。
「・・・・・」
帰って来ない。
誰が、なんていわずもがなだ。
あれからだいぶ経っているなと薄暗くなってきた外を見て思う。
やっぱり、自分には人を見る目が無いのだろうか。
でも、渡したお金を盗られたと悔やむ気にはなれない。
もしそれで彼の生活が何か豊かになるなら、まあそれでいいかと思うくらいだ。
それにしては少ないだろうけど。
どういう服を買うのか良く分からなかったから、とりあえず1万円を渡しておいた。
受け取ったときユーリはポーチの中を見なかったから、その金額にどういう反応をしたのか良く分からなかったけれど。
「舌打ちとか見なくて良かったかも」
「・・・舌打ち?」
「!?・・あ」
「ただいまって・・なんだよ、その顔」
片手に紙袋をぶらさげて、出て行ったときとなんら変わらない姿のままの相手が目の前に立っている。
思わず浮かべてしまっていたのであろう、有り得ないものを見たという表情は、すかさずユーリに見咎められる。
無言で窓口を通り過ぎて行くのを眺めてから、慌てて玄関の鍵を開ける。
「・・・ただいま」
ふてくされたような顔。
「お、おかえり・・・遅かったね」
帰って来ないと思っていたわけじゃない。
信じてなかったわけじゃ無いけれど、そう思っていたように見られても仕方が無い反応をしてしまったことに、何故か後ろめたくなる。
その後ろめたさに言い訳をする。
遅かったのが悪いんだと。
ああ、結局相手のせいにして、自分を正当化させようとしている。
・・・醜い自分の心。
「はあ・・・そんな顔すんなって」
「・・・ごめん」
「・・・謝んなよ。遅かった俺が悪かった。にはそういう顔する権利がある」
「権利があったとしても、信じているつもりだった・・!」
そう言えば、目を丸くしてふっと笑う。
身長差から少し見下ろしてくる瞳が柔らかく笑って。
「!っや、何・・」
「そう言ってくれるだけで、十分だ」
大きな手が伸びてきて、ぽんぽんと頭を撫でられる。
まったく、これでは立場が逆な気がする。
「そ、そういえば」
「んー?」
撫でる手を何とか退かせて、まだ何だか嬉しそうな相手の顔を見上げる。
「ユーリは何歳なの?」
「俺?俺は21」
「!!!・・・若い!」
「・・え?」
「え?」
大学生だ、さすが若いなと納得していれば、丸くなった目がこちらを見ている。
「・・・えっと、聞いていいのか?」
「・・・・四捨五入で30になるけど」
まだ30じゃないからね、とどうでもいい念押しをしてしまうのは仕方が無いだろう。
乙女心を理解しろとは言わないが、ぼかしたい気持ちは許して欲しい。
「・・嘘だろ」
「嘘じゃないけど・・何よ」
「あ、いや・・てっきり俺より年下かと思ってた」
顎に手を当てて、しげしげと見下ろされる。
いや、21より年下とか、それだったらもっと学生生活を満喫してるわ。
思ったより過去になっていた大学生活を、少し遠い目で思い出す。
「・・ええと、それでいいもの買えた?」
「ん、ああ。ありがとうな」
ごそごそと紙袋の底から返された花柄のポーチを受け取る。
閉じられたチャックを開ける。
「え、ちゃんと買えたの??」
お札がいっぱい残っている。
「もちろん、ちゃんと買ってきたぜ。ってか1万とか、渡しすぎだろ」
「だって、どんな服を着るとか何が必要とか、とっさに思い浮かばなかったし」
「それにしても、だ。多すぎ。そんなにいらねえって」
それじゃあ、一体その紙袋には何が入っているというのだろう。
「何だ?気になるってか?」
「あ、いや別に・・」
いい、何でもないと両手を振る前で、紙袋をごそごそと漁って、買ってきたものを並べ始める。
「ごめん、本当に報告させたいわけじゃなくって」
「そういうわけじゃねえって、分かってる」
このシャツとパーカーが安くってさーと、紙袋から取り出してみせてくれる。
犬のシルエットの入った少し暗めの水色の長袖のシャツと、黒いフードつきのパーカー。
同じく黒い無地のパンツ。
縦のライン入りのスポーツウェア。
「何で・・・小豆色・・」
まるで学生のジャージみたいだと思えば、胸元に名前が入っている。
「え?田中って・・・田中?」
思わず胸元に刺繍されていた名前と、ユーリの顔を見比べてしまう。
視線が合った相手は、思いっきり呆れていた。
「・・・んなわけねーだろ」
「だよね」
「商店街のおっちゃんに聞いて、ちょっと歩いたとこに古着屋があるって言うからそこに行って来てさ。ジャージは、古着屋の人がお古っつって、タダでくれたんだよ」
「そんな、わざわざ遠くまで・・」
「わざわざってほど遠くでも無いっての。・・でも、悪かった」
「え」
広げた服をくるくると丸めて、また仕舞いこんでいく。
しゃがみ込んでいるそのつむじを見下ろしていれば、ふっとその顔がこちらを見た。
「心配させて、悪かった」
「そんなのは・・勝手にしたことで、ユーリが謝ることじゃない」
「嫌なこと考えさせちまっただろ」
「・・・・・」
無言で、その頭を上から撫でる。
さらさらだ。
手の平に気持ちよくって、ゆっくり撫でるを繰り返す。
「・・・何か、犬になったみたいだ」
床にしゃがみ込んで、撫でられるままになっている、その長い髪の下からぼそっと呟かれる。
その何となくふてくされているような、納得がいかないような声音に思わず笑いが漏れる。
「ふふ、私のペットにでもなる?」
冗談で言ってみる。
彼氏とも別れて、会社も辞めた。
新しい生活にはもう、これ以上は無いっていうくらい楽しい刺激を体験している。
そう、何だかすごく楽しいのだ。
親戚のつてでもあるし色々融通してもらったのもあって、話し合いで賃金は少し安めにしてもらった。
前より収入は格段に下がるけれど、前の会社で働いていた分の貯金もいくらか貯まっている。
お金のことをこんなに考えているなんて、何だか彼を囲ってもいいなんて思っているみたいだ。
まあ、冗談だけど・・・。
「・・・いいよ」
「だよね、って・・ぇえっ?」
ペットとか冗談じゃないって言われるだろうと思っていたところに、帰ってきた返事に一瞬聞き間違いかと思う。
「いいよ、あんたのペットでも」
「いや、良くないでしょ。人権を放り投げるんじゃありません」
せめてなるならヒモでしょうと言いそうになって、結局それのどこが違うのかよく分からなくって首を傾げる。
すっかり動きを止めていた右手に、するりと相手の手が絡まってくいと引かれる。
続いて、すり寄せられた頬に驚いて手を引っ込めようとした。
すべすべだとこのやろう、羨ましい!
「はっ、離して」
「飼ってくれるなら、離す」
何だその、脅し。
ぎっと固まる手の平に顔を寄せて、少し意地が悪そうな笑みを浮かべてこちらを見る相手を、信じられない思いで見下ろす。
馬鹿じゃないの?
そう言ってやれば良いのに、混乱して動きが鈍った。
その瞬間、手の平にぬるっと湿った感触。
「ゴホウシしますよさん」
「!!!!っ」
ちらりと覗いた舌先に、今度こそ全力を込めて右手を取り戻す。
その手を拳に変えて振り下ろす。
「調子にのってんじゃないわよ!」
広くは無い部屋の中に、鈍い音が響いた。
◆アトガキ
2013.10.30
色んなネタがやりたいけれど、まだじりじりと進めて。
やっとこの設定にたどり着けました。
臙脂色のジャージでポニーテールして欲しい。
白いハチマキ似合いそう。
・・・・・。
・・・もう女の子にしか見えません。
icon by Blancma
background & line by web*citron