拾ってください。
一
「・・・よし!」
何も置かれていないキッチン。
部屋の床の四角の隅まで見えるフローリング。
カーテンのかかっていない窓。
床に置かれた幾つもの四角い箱・・・ダンボール箱だ。
それらを見つめて、気合を入れる。
今日からここが私の新しい城。
前に使っていたという知人はしっかり綺麗にしてくれて行ったようで、先に一度掃除でもしなければならないかもと思っていたので助かった。
開け放った窓から入ってくる爽やかな風に、夕暮れの涼しくなる前に片付けてしまおうと腕をまくる。
イヤホンからお気に入りの曲を流しながら、ガムテープをはがして箱を開封していく。
「・・・・~♪」
わくわくしている自分に苦笑するも、どうにもそんな気持ちが止まらない。
何も無いまっさらな場所に自分のものを好きなように配置していく。
徐々に埋まっていく空間に、心が暖かいものに包まれていくような幸せと充足感を感じる。
新しい生活というものに、何も不安が無いわけではないけれど。
一度自分をリセットして、今日からまた再スタートだ。
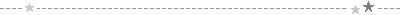
「じゃあ、後はよろしくね」
「ありがとう、おばさま」
「いいのよ。こっちもどうしよう迷っているところだったんだもの。助かったわ」
ふっくらとした頬をにこにことさせて叔母さんは笑う。
「全く・・。うちの子もやっと自分から何か動き出したかと思えば海外だなんて、呆れちゃうわよねえ」
「いいえ、あいつらしいです」
そーお?と頬に手をあてる叔母に、いとこの姿を思い出して頷く。
大学を数年留年してやっと卒業したかと思えば、何をするわけでもなく。
叔父の所有しているアパートの管理人を数年やったかと思えば、海外に留学するだなんていってリュックサック1つでさっさと出かけてしまった。
小さい頃からふらっとどこかに出かけては、擦り傷と笑顔で帰ってくるようなやつだ。
そもそも、英語なんて出来たのだろうか?
そっちの方が意外だが、所謂天才肌で何でもそつなくこなすやつだったから、まあどこでも順応して生きていけるだろう。
「心配いりませんよ、おばさま。気が付いたらふらっと戻ってきますって」
「まあ・・・そうよねー。でも年末はいてほしいわ」
何だかんだで一人息子がいないのは寂しいのだろう。
苦しいときに相談にのってくれたおばさんの小柄な肩を、ぎゅっと抱きしめた。
「私でよければいつでも!」
「あらまあ、嬉しいわ」
ふふふと笑って背中をぽんぽんと叩いてくれる。
私より小さくても、とても暖かい手だ。
最後にもう一度、部屋は1階だからくれぐれも気をつけてね、と念押しをされて私はその鍵を受け取った。
アパートの管理人の部屋。
私の新しい職場、兼住居だ。
「ありがとうございます。よろしくお願いします」
「ええ、よろしくね」
手を振って歩き出す。
アパートは叔母の家からは数駅離れたところにある。
今まであまり使ったことのない路線の電車に乗って、何度かは行ったことのあるそのアパートへの道を辿った。
「・・・・・」
電車の窓から流れる景色をぼおっと見る。
思い出すのは、辞表を出したときの社長の顔と別れを告げたときの彼氏の顔。
どちらも驚愕と、そして前者は困惑、後者は怒ったのか顔を真っ赤にしていた。
残業も多かったけれど社長にはよくしてもらったこともあり、4年も働いていた職場を離れるのは勇気がいった。
それでも、あのままあそこに残る気にはなれなかった。
職場恋愛なんてした自分が悪かったのだ。
自業自得だ。
「・・・・・・・・」
それでも、納得し切れていない想いもある。
親戚の好意で次の職にすぐにつけなかったら、私はどうしていただろう。
苦しくて辛くてもあの場に残っただろうか。
駄目だ。
こうやって考え出して堂々巡りを繰り返しても、もう終わったこと。
これからの新しい場所での生活に気持ちを切り替えて、今までより少しゆっくり過ごそう。
そう、何しろ朝から通勤電車に押しつぶされそうになることは無いのだ。
高いヒールで足を痛くする必要も、営業先のセクハラ紛いの親父の相手もする必要なんてない。
そう思えば、強張っていた頬から力が抜けていく。
窓の外の風景も何だか明るいものに見えてきた。
部屋を確認して、明日引越しが済むまではまた一度元の家に戻るけれど、その前に最寄の駅で商店街をぶらつこう。
食材や日用品が安く買えるスーパーを確認して、それから美味しそうなお昼を買おう。
小さな子どもに戻ったみたいに心が浮き足立つ。
そんなことを考えていたら、いつの間にか降りる駅に到着していた。
電車の、扉が開いた。
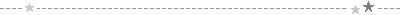
鼻歌を歌いながら棚の中に食器を収めて、クローゼットの中に衣類を仕舞いこんでいく。
今まで使っていた使いやすいものだけを残して、他は全部捨ててしまったからまだまだ殺風景かもしれない。
それでも風に翻るチェックのカーテンに心は和むし、自分だけの空間だから本を置けるスペースもいっぱいとれて嬉しい。
空きスペースを見ると、後何冊置けるだろうと頬も緩む。
商店街のどの辺りに本屋はあったかと思いながら、トイレに小物を仕舞いこんでいてふと気が付いた。
「あ、トイレットペーパーが無い」
消耗品はこっちで買おうと思っていたのに、トイレットペーパーだけ忘れてしまっていた。
かさばるから後にしようと思ったのが失敗だ。
近所の学校から5時の鐘が鳴っているのが聞こえる。
のどかな音楽に、ついでに夕飯も買っちゃおうかなと思う。
今日は一日動いて疲れたし、引越し蕎麦的な何か暖かいものがいい。
これ以上肌寒くなる前にとコートを羽織って、財布を持つ。
管理人は出かけている旨を示すプレートを窓口に置いてから、夕方の商店街へと一歩足を踏み出した。
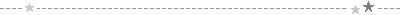
夕飯も食べて暖かいカフェオレを飲みながら、管理人窓口の椅子に座って本を読む。
とはいえ、時刻はもう10時も回っている。
窓口は7時で閉めても良いと言われたから、表示を変えて窓口のカーテンは閉めているのだが、この小さな書斎のような窓口スペースは思いのほか居心地がいい。
いとこが置いていった座り心地の良いゆったりとした背もたれのある椅子とか、足元を暖める小さな暖房器具、そして棚に置かれた注意事項などもろもろの内容の本やファイルと、居住者のいない間に預かっている荷物などが置いてあって、本当に狭い小部屋。
窓口のガラスは薄いからさすがに直に音を出すのは躊躇われて、イヤホンからの音楽に耳を傾ける。
「・・・、・・・・?」
ふとゆったりとした音楽の向こうで何かの物音が聞こえた。
外からだったから、誰か住人が帰ってきたのだろうか。
それにしては、だいぶ重そうな音だったけれど。
カーテンを開けて様子を見ようか迷うが、それ以上何の音も聞こえないことに意を決して立ち上がった。
コートを羽織ってサンダルを履いて、扉を開ける。
そろりと扉の外を確認するも、人の気配はない。
聞き間違いだったのだろうか。
このアパートは大通りや商店街からは少し入ったところだから、この時間ならもう家に帰宅する人ぐらいしか前の道を通る人はいない。
そう思ったのだが、確かに何かの物音がしたような気がした。
「・・・・・・」
外に出てアパートの自動扉を抜ける。
一歩、道路へ足を踏み出して左を見て、次に右を・・・。
「!!・・・え?」
思わず2度見してしまった。
そこには自分の引越しに使ったダンボールが置いてある。
丁度次の日が古紙回収の日だったから、さっさと縛って住人の出した分と合わせて、玄関前のそれ用のスペースに重ねて置いたのだ。
ちゃんと、畳んで、紐で縛って・・・置いておいたはずなのに。
「・・・・え、なんで?」
何故かその1つがまた組み立てられている。
布団などが入っていた少し大きめのダンボール箱だ。
怖い。
こんな真夜中に謎のダンボールとご対面してしまうなんて、管理人じゃなかったら見なかったことにして部屋に戻って寝たいぐらいだ。
でも、このアパートにおいては、残念ながら自分がその管理人で。
つまるところこういった厄介ごとも、自分が対応していかなければならないのだ。
このまま放っておくわけにはいかないだろう。
「・・・・・・よし」
たっぷり数分、ダンボールと見詰め合って覚悟を決める。
一歩、また一歩と恐る恐る近づいてみる。
蓋は少し浮いていて、完全には閉まっていない。
手を伸ばせば開けることが出来るだろう。
隙間の暗闇から中を覗く勇気は、無い。
そんなことをするくらいだったら、ばっと開けて最悪すぐに回避できるように出来るだけ体を遠ざけたまま中を確認出来れば。
「・・・・・でも」
どうしよう。
中に得体の知れないものが入っていたら。
ごみが捨てられているとか、何か臭うくらいだったらまあ頑張って対処できないことも無いだろう。
でもこの距離でそういった臭いはしない。
本当に、何でもないものであればいいのだ。
・・・・・怖いものや、生ものが入っていたりしなければ・・良い。
自分で考えて伸ばしかけた腕が止まる。
どうしよう・・・開けて中のものと目が合ってしまったら。
「・・・・ホラーの見すぎ、よね」
大丈夫、大丈夫と言い聞かせて、腕を伸ばしてダンボールの蓋の端っこを掴んで、えいやっと外側に開いた。
即、腕を引っ込めて中をちらっと見て、慌てて目を瞑った。
・・・い、今なんか腕が見えたような気がする。
腕?!・・無い無い。
「・・・そんなことあるはず無いわよね・・腕、なんて」
でも、眼裏に焼きついたその白さに血の気が下がる。
まさか、いやでも、まさか・・・死体?!
「!!!!?」
死体なら動かない、そう思った瞬間に呻き声のようなものが聞こえて、肩を大きくびくつかせてしまった。
声?・・・生きてる?!
慌ててダンボールに駆け寄って、中を覗き込む。
今度ははっきりと見えた。
「え?・・女の子?!」
ぐったりとした髪の長い女の子が、ダンボールの底に横たわっている。
何てことだろう、葛藤していた十数分を巻き戻したいぐらいだ。
もっと早く開けて、様子を見てあげれば・・。
「!・・救急車?いや、警察?・・救急車が、先よね」
いやいやそんなことよりまず、この状態からどうにかしたほうが良いのでは?
暗くてよく見えないけれど、もし怪我をしているのなら何をするよりまず先に手当てをしなければ。
「ちょっと、あなた大丈夫?!」
声をかけても返事が無い。
ダンボールの底に両手を伸ばして、両脇に回して抱え上げる。
思ったより重い、そして・・背が高い?
片方の脇に自分の肩を入れて腰に手を回し、足を踏ん張って立ち上がった。
体が冷え切っていることに恐怖する。
このまま、ここで死んでしまうんじゃないか。
それは、駄目。
管理人だからとかではなく、まだ生きているんだから助けなければ。
それだけを考えて、必要以上に揺らさないように気をつけて何とか部屋に運び込む。
ベッドに横たえて一息つく間もなく、管理人窓口の小部屋に置いていた暖房器具を運んでスイッチを入れる。
布団をかける前に、明るい部屋の中で怪我が無いかを確認する。
自分の両手を見て、そこにも赤いものがついていないことを確認する。
それでも一応、と一言謝ってからもう一度その両脇に腕を回して、体を引き起こした。
「・・・・・ん?」
正面から抱きしめるような格好になって、ふと気が付く。
胸が無い。
いやいや、胸があまり無い人なのかもしれない。
こんなに綺麗な長い髪をしているのだ。
胸など無くても美人・・・・。
「・・・・、・・っ」
少し体を離して、目の前の眼が閉じられたその顔をまじまじと見てまた驚いた。
本当に綺麗な顔立ちをしている。
背も高いし、綺麗な黒髪にこの顔つきなら、モデルさんだろうか。
すらっとした体型にも納得する。
そのとじられた眉の上で眉根がピクリと動いて、うっすらと瞳が開く。
ぼんやりとした目が、こちらを見たような気がした。
ちょっと驚いたような、そんな風に見えたと思ったのだが、その瞳はまた閉じられてしまった。
「・・・外人さん?」
髪で影ができていてよく見えなかったけれど、瞳の色が黒とは少し違うような気がした。
気のせいだろうか。
とにかく、外見には異常は無さそうだ。
何だか釈然としないものを感じながらも、もう一度ゆっくりと横たえてその上に布団をかぶせる。
体が暖まったのだろうか、辛そうな様子も何も無い。
それなら一晩寝かせてあげて、明日起きてから話を聞けばいい。
救急車を呼ばなければいけない様子は無く、警察を呼ばなければいけないほど怪しい風体では無かった。
ほっとしたら、急に疲れと眠気が襲ってくる。
「外の、ダンボール・・・」
片付けなければ。
そう思ったけれどどうしても眠くて、部屋の暖かさも相まってベッドの横に座り込んで目を閉じた。
◆アトガキ
2013.10.29
はー。
衝動の赴くままにキーを打てるのって幸せです。
書きたくても打てない時は辛い。
やりたいネタを仕事中にずっと考えていたりして。
すでに幾つか上がっているので、キーを打てる間は綴っていこうかと思います。
icon by Blancma
background & line by web*citron