世話してください。
一
朝だ。
目覚ましは鳴っていないけれど、習慣が身についているのか勝手に目が覚める。
今何時だろうと目覚まし時計を手に取ろうとして、手を伸ばして・・そして壁に触れる。
「・・・・あ、れ?」
ぺしぺしと何度か壁を叩いてから、ああここはもう新しい部屋で時計はこっちでは無いのだと、ぼんやりと動き出した脳内で考える。
ならば、どこに置いたのだろう。
暖かい布団の中でもぞもぞと動いて、頭上に手を伸ばした。
「・・・??」
今何か、布団の中でぶつかったような気がした。
何だろう、何か固い・・・そう本とか読みながら寝ちゃって布団の中に本でも入ってしまっているのだろうか。
「・・ん・・」
「・・・・・へ・・え?」
目を開く前に、耳に入ってきた音に脳が一気に覚醒する。
音じゃない、それは自分以外の誰かの声だ。
慌てて布団をめくろうとする前に、もぞっと動いた何かに体当たりされる。
腰に細長い何かが巻きついて・・・これは腕?
「だっ・・誰?!」
「・・ん、あと、少し」
寝ぼけたような低い声で返事が返ってくる。
あと、少し、なんだと言うのだ。
勿論、後少しなど待てるはずも寝させるはずも無い。
無言で布団をがばっとはねのけた。
「!!!あなたっ」
布団の上に散らばった長い髪を見て、昨夜のことを瞬時に思い出した。
ダンボールの底に倒れていた女の子だ。
・・・女の子?
確かに、髪も綺麗で顔立ちも綺麗で、これらは昨日見たときも思ったのだけれど。
でも、これは・・・・・。
無言で布団をはがした右手を振りかぶって、振り落とした。
「・・いてっ」
「起きてちょうだい」
今度こそ目を薄っすらと開けた相手に訴える。
ついでに、この腰に回されている腕!
「ちょっと・・離れて!」
「・・・ってえ・・殴ることはねえだろ」
「殴らずに、いると思うの?」
「・・・・・」
自分でも、起き抜けにしても低い声だったと思う。
そろりと腕を引き寄せて上半身を起こした相手の横に、並んで起き上がる。
改めて朝日の中で見れば、女の子にしては体がしっかりとしている。
がしがしと頭をかく手は大きく、そして何より。
「前を!しめて!!!」
「・・・ん?」
昨日はそんな乱れは無かったはずの、シャツの前が盛大にはだけていた。
体がしっかりしているとか、そういう話ではない。
完全に上半身が見えている。
綺麗な鎖骨とか、程よく筋肉がついた上半身とか、朝っぱらから見るにはきつい。
色気のような何かが駄々もれていて、彼氏もいた身だというのに直視は出来なかった。
「シャツ!ボタン!」
「・・・ああ」
綺麗な紫色の瞳が瞬きをして、やっと分かったのかシャツのボタンを留めていく。
さらさらと長い髪が動きに合わせて揺れている。
思わず自分の髪に手をやって、その絡まり具合に落ち込む。
というか、いくら自分が相手と壁の間にいるからといって、相手がシャツのボタンを留め終わるまで待つ必要はない。
無言でずりずりとベッドを這って降りようとした。
「・・・・何?」
「どこ、行くんだ?」
真剣な顔をした相手に、言葉が喉に詰まる。
どこへと聞かれても、それはもちろん、この寝室に当てたワンルームを出た先の、居間兼キッチンスペースへだ。
脱いだ覚えのないコートがしっかり壁に掛けられているところを見れば、そのポケットの中の携帯に手を伸ばすのも馬鹿らしい。
居間へいけば、備え付けの電話が置いてある。
もちろん、警察へ電話するつもりだった。
「・・・・・トイレ」
「・・嘘だろ?」
「・・・・・」
正直に言うわけが無いじゃない。
そんなの何をされるか分からない。
すでに何かされていたらと思えば、血の気が下がって指先が冷たくなった気がした。
手首を掴んでいた相手にもそれが伝わったのか、少し困った顔をしている。
そんな顔をされても。
こっちが困っているんであって、相手にそんな顔をする権利は無いはずだ。
「通報とかは・・・しないでくれないか?」
「そんな約束、出来ると思う?」
「・・・・思わねーけど・・・頼む」
「・・・・・・」
困った顔、少し真剣な顔、・・・これだから顔のいい奴は。
そう思うのに、通報する気は失せていってしまう。
憶測で物を考えるのではなく、もう少し猶予をやっても良いかな、なんて。
とりあえずダンボールの中にいた理由ぐらいは聞いて、それから出て行ってもらおう。
「はあ・・・分かった。通報はしない」
「・・・!!・・サンキュ、助かる」
自分で頼んでおいて、驚いたように丸くなった瞳がふっと細められる。
本当に嬉しそうなその笑顔に、何か見てはいけないものを見てしまった気になる。
「分かったら、離して欲しいんだけど」
「あ、ああ、わりぃ」
「・・・・・」
「・・・・・」
掴まれていた手首が離されて、ベッドの上に座り込む。
離した左手をあぐらをかいた足の上に置いて、相手もこちらを見ている。
何を言ったらいいか、何から聞けばいいか。
分からずに口を開きかけて、やめる。
こちらの言葉を待っているのか、相手はじっと黙ったまま動かない。
「えっと・・・あなた、名前は?」
やっと出てきたそんな問いかけに、きょとんと瞬きが返ってくる。
そうかと思えば、ふっと微かに息が漏れる音がして、相手が笑ったのだと分かった。
思わずむっとする。
「何・・」
「ああ、悪い。悪かったから、怒るな。あんたが何か可愛いくて、つい」
さらっと言われて、今度はこちらが瞬きをする番だった。
何だ・・・ホストとかそういう類の人間?
ああ、そうか外人さん?だからかな。
こんなことさらっというやつっているんだなと、しげしげと見つめ返してしまう。
・・・しかもそれが、違和感なし。
つくづく、顔立ちって大切だなと思う。
・・・・そうか、やっぱり世の中、顔か。
加えて、思い出した嫌な出来事に表情が歪む。
「・・・って、どうしたんだよ。ああ、えっと俺の名前だっけ?」
「何かもう、どうでもいい」
ちょっと捨て鉢になる。
何かされちゃってようが、いきなり見ず知らずの男と同衾してしまったことだとか、そんなことどうでもいいかと思う。
もうそういったことにおいては大きなダメージを負ってしまったから。
それが治るまでは、他の些細な怪我なんてどうってことない。
・・ないっていったら、ない。
「よく分からないけれど、あなた元気そうだし」
「・・・・まあ」
そう、だなとぽつりと呟く相手に、笑みを返す。
「じゃあ、大丈夫よね。・・・出て行って?」
「いや・・えっと」
「一泊させてあげたんだから、もう良いわよね?」
「・・・・・」
こちらの顔を窺って、相手はちょっとだけ眉を寄せた。
「何で、笑えるんだ?」
「・・・・・え?」
「普通、こんなことになって笑うようなやつ、いないだろ」
俺が言うのもなんだけどよ、と付け加えられる。
確かに言う権利は無いだろうと思うが、答えられない。
「そんなこと言う必要も無いでしょう」
だって、もう出て行く相手だし。
何も知らない他人だし。
だから、少しでも穏便にことを収めようとしているだけだ。
こんな風に突っかかられる謂れは無い。
「・・・名前は、ユーリ」
「・・え?・・や、ちょっと待って」
「待たない。呼び捨てでいい。んで、俺は今、行く宛てが無い」
「待ってってば!ちょっと、止めて・・・」
「旅行しに来たら、荷物を全部盗まれて、頼る宛ても何も無い」
「・・・・・・・・・・旅行?」
「そう、財布もねえんだ・・・」
怒涛の自己紹介を聞いて、やっぱり外国の人だったのかとその綺麗な瞳を見て思う。
それにしては日本語堪能だとも思うけれど。
「少しの間でいい・・・泊めてくんねぇ?」
一瞬、捨てられた子犬に見えた自分の目は、おかしいと思った。
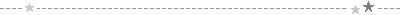
「・・・で、荷物を盗んだ相手を追いかけたらタックルされて意識が飛んで?」
目覚めたらこの部屋にいた、と。
頷く相手に、片手に持っていた珈琲をテーブルに戻して、溜息を吐いた。
今は、取り合えず朝食にしようと、焼いたトーストと珈琲を挟んでダイニングテーブルに向かい合って座っている。
食っていいのかと聞かれて、今更駄目というわけもなく。
頷けばその目が輝いた、気がした。
ザカザカとトーストにバターを塗って、イチゴジャムの蓋を開けて、そして目をうろつかせる。
「・・・・・はい」
「!どーも」
手元にあったまだ使っていないバターナイフを渡せば、驚いて、そして少し笑う。
嬉しそうにイチゴジャムを塗りたくっている相手に、こっちは脱力しっぱなしだ。
仮にその旅行話が嘘だとしても、もう怪しむ気さえ起きない。
どうでもいいとかではなく、今度こそ警戒心がなくなってしまった。
「いただきます」
「・・・召し上がれ」
変なところ、律儀だ。
大きな口で、何回かトーストを齧って。
あっという間にペロリと一枚食べきってしまった。
「・・・・食べる?」
どう考えても、一般男子のその体格の腹を満たせる量では無かっただろう。
そう思って、自分の皿をそちらに寄せる。
「・・・いや、これはあんたの分だろ」
「いいよ。元々、朝はそんなに食欲が無いの」
「・・・・・じゃあ」
皿からトーストを取り上げて、半分に割る。
割られた半分が返ってきた。
「しっかり食べろよ」
「・・・・・」
「まあもともとあんたのだけど・・・それにしてもあんた、よく見ると顔色悪い」
「・・・あんたじゃなくて、」
押し戻された皿の上の、半分になったトーストに手を伸ばす。
「・・・・」
「・・・何?」
名前を呼ばれたから、バターを塗っていた手を止めて顔を上げれば、何故かすっと視線がそらされた。
「??何よ」
「・・・何でも、ねえ」
あ、そう、とまたバターを塗る作業に戻る。
トーストを食べる。
もぐもぐと咀嚼をしていれば、向かいがやけに静かでついまたそちらを見てしまう。
目が合えば、ふっと視線が揺れる。
何だろう。
何でもないといったくせに。
無言のままトーストを食べ終える。
楽しい会話をしたわけではない。
ただ、そこに人がいただけだ。
「・・・・・・」
食後にまた珈琲を淹れ直して、それを飲みつつ何とも不思議な気持ちになる。
一人では無いだけで、ご飯を食べるという作業が少しだけ苦では無かったこと。
それが、不思議だ。
向かいの相手は、珈琲の水面を見ている。
「どうしたの・・・・・ユーリ」
ちょっと迷って、自分も名前を呼んでみた。
黒い珈琲を見ていた瞳がすっとこちらを見る。
何か言いかけて、口を閉じる。
首を傾げてそんな相手の様子を見る。
猫舌、なのだろうか。
だとしても、2杯目の自分に対して、相手のカップに入っているものは最初に淹れた1杯目だ。
とっくに冷め切っているだろう。
「レンジで暖めようか?貸して」
「いや・・・・」
何となく歯切れ悪く、逡巡した後にそっと差し出されたカップを受け取る。
レンジで暖めつつ、その扉に映る背後の人影を盗み見る。
向こうも、何だか良く分からない顔で、じっとこちらを窺っているように見える。
電子音が鳴って、レンジの光が消えた。
またほかほかと暖かくなったカップを手渡せば、少し眉が下がった。
困っている顔だ。
・・・・もしかして。
「気付かなくてごめん。・・はい」
自分は入れないからといって、誰でもブラックで飲めるわけでは無いことに、やっと思いつく。
スティックシュガーなんてものは常備していないけれど、紅茶をミルクティーにして飲むこともあって珈琲フレッシュはある。
冷蔵庫から出したそれと、料理用の砂糖の入れ物をテーブルに並べる。
「!!・・・サンキュ」
当たり、らしい。
暗かった瞳にぱっと光が煌いたような気がした。
いそいそと砂糖を掬って入れ、ミルクを入れている。
・・・・さすがにそれは多くはないだろうかと心配になるぐらい入れて、無言で差し出したスプーンを礼と共に受け取って、ぐるぐると中をかき混ぜている。
ブラックだった水面は、ミルクティーかと言いたくなるほどの甘みを帯びた薄茶に変化している。
持ち上げて一口飲んで、頷いている。
「・・・甘すぎじゃない?」
「いや、丁度いい」
「・・・そう」
まあ、本人がそういうなら飲み方は人それぞれ、好きにするべきよねと自分のブラックコーヒーの入っているカップを持ち上げて一口飲む。
何だか、自分のコーヒーも甘ったるくなったような気がした。
◆アトガキ
2013.10.29
ちょっと無理がありそうですが、旅行者設定で。
ほら、目の色がね。
・・・黒目にしちゃってもいけそうっちゃいけそうですが。
ちなみに、テルカ・リュミレースからのトリップ旅行者、とかじゃないです。
世界は跨ぎません。
icon by Blancma
background & line by web*citron