一
久しぶりに、ちょっと飲んでみようかと思って。
「ブランデーと・・・そこのリキュールは何のリキュール?」
「また女将さんのお使いかい?」
「ああ、うん、そんなとこ」
自分で飲む用だと言えば、相手によっては売ってくれなかったりする。
イーストシティの酒場でも軒並みそんな反応だった。
どんなに飲めると言っても、笑ってノンアルコールカクテルを出される。
まあ、シャーリーテンプルも嫌いじゃないんだけど、さすがにオレンジジュースを出された時は落ち込んだ。
「これはチョコレートのリキュールさ」
「じゃあ、それもお願い」
「酒場でこんな甘いの出すかい?」
「あ、いや製菓用にどうかと思って」
ちょっと訝しげになる顔に、慌てて言い繕う。
半分は本気な分うそ臭さが半減したのか、そう言えば店の女性は納得したように、外装に包まれたまるっとした瓶もまとめて紙袋に詰めてくれた。
重いから気をつけるんだよと見送られながら箒星に帰った。
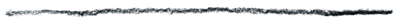
「・・良い匂いだな」
ふらりと出掛けてはいつの間に帰ってきたんだか、自分と同じく上の宿屋を間借りしているユーリが厨房に入ってきた。
すんすんと匂いを嗅ぐ様が、自身の相棒とそっくりだ。
「チョコレート?」
「ああ、ブランデーを買ったからガトーショコラに」
きらりと輝く紫がかった黒い瞳。
こういうところはまるで少年だ。
「は意外と菓子作りが上手いよな」
「余計な一言が混じってるな。やらんぞ」
「すいませんでしたさん」
即座に謝るくらいなら言わなけりゃ良いと思うんだが、性分なんだろう。
・・他人に傍迷惑な性分だ。
使った器具を後片付けしながら、オーブンの中の焼き具合を確認する。
どうやら、上手く焼きあがりそうだ。
お昼の時間も過ぎて、夜の仕込までの合間に借りた厨房に甘い匂いが漂う。
ついでにとミルクパンを取り出して牛乳を注いで火にかける。
チョコレートのケーキにチョコレートのリキュール入りのホットミルクなんて甘ったる過ぎるとは思ったのだが、チョコとミルクの相性が良いのが悪い。
がさりと紙袋を漁って、新しいリキュールの瓶の蓋を開けた。
「それは?」
「・・・・・」
焼きあがるのを待っているらしいユーリに、リキュールを指差されて 一瞬答えあぐねる。
チョコレートのリキュールだと正直に答えたとしよう。
俺の分もよろしく、といった答えが返ってくるのが目に見える。
そういえば、こいつは何歳だ?
酒は飲めるんだろうか。
「・・何だよ?」
押し黙ったままの自分に、訝しげな声がかけられる。
「ユーリはいくつだ?」
「いくつって、歳のこといってんのか?20だけど」
「そっか、なら大丈夫だな。これはチョコレートのリキュールだ」
「ふうん、は酒飲めるのかよ。そもそも、そっちこそいくつなんだ?」
「ユーリと同じようなもんだ」
「何だそれ、曖昧だな」
孤児だったし、長い間研究所の中にいたから正確な歳なんか分からない。
まあ、おそらくはそんくらい、だ。
追求しようか迷う素振りを見せる相手からさりげなく目をそらして 首を竦めながら、マグカップを2つ取り出す。
「俺の分も淹れてくれんのか?」
「待ちきれずにわくわくした瞳を隠せずにいる甘党の少年の歳を疑ったお詫びだ」
「・・・お前は一言も二言も余計じゃねえか」
タイミングよく沸騰した牛乳をそれぞれのマグカップに注いで、リキュールを足してスプーンでくるくると混ぜる。
ふんわり甘いミルクチョコの香り。
自分の分にふうふうと息をかけて冷ましつつ、もう1つを傍に立つ相手に渡す。
「やっぱ猫舌なのか?」
「悪いか」
「いんや」
受け取った相手は熱さをあまり気にせずに、一口飲んで目を細めた。
猫と掛け合わされた自分より、猫っぽい気がする。
「これ、いいな」
「そうか良かった」
少しばかり冷めた自分の分のマグカップに口をつける。
程よい甘さと、温められたアルコールが体を心地よい温もりで満たしていく。
静かな一時に、焼けたことを知らせるオーブンの音が響く。
ミトンをはめてトレーを取り出す。
少し焦げるようなくらいがほろ苦くって好きだから、この焼き具合なら良い出来だろう。
調理台の脇に置いておいたマグカップが横から伸びた手に持っていかれる。
「おい、それは私の」
「いいだろ、もう1回作れば」
いつの間に自分の分を飲み干したのか、人の分のミルクチョコまで飲みながら、もう片方の手でミルクパンに牛乳を注いでいる。
そんなに度数は強くはないはずだが大丈夫だろうか。
竹串に生地がくっついてこないのを確認して、上に粉砂糖をふりかけつつ横目でその様子を窺う。
ユーリは鼻歌を歌いながら牛乳が沸騰するのを待っている。
飲み終わったのか、名残惜しそうに口元をペロリとひとなめしているのなんて、食いしん坊の少年にしか見えない。
・・背だけは無駄に高いのだが。
その横顔に特に顔に赤みが指している様子も無い。
飲んでいるところを見たことは無いが、酒には強いのだろうか。
まあ、成人も迎えているわけだしそう心配することも無いか。
かくいう自分も飲まれてしまった分、もう少し飲みたい。
作ってくれるならとそっちは任せて、切り分けたガトーショコラを皿に盛ってフォークを添えた。
「どこで食べるんだ?」
「部屋でのんびり食べようかと」
残りを女将さん用にと包んで冷蔵庫に仕舞いながら、マグカップとリキュールを持つユーリに返事を返す。
「んじゃ、俺の部屋でいっか」
「いや、まあどっちでもいいんだけど」
さっさと先を行く相手の後ろを、二つの皿を持って追った。
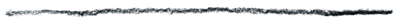
「これは・・美味いな」
「そうか良かった」
フォーク片手にしみじみと言う相手に、そこまで感動してくれるんなら作り甲斐があったと思う。
いつだったか、この世界に来てふとアップルパイが食べたくなって、女将さんに厨房を借りて作った時のユーリの顔を思い出した。
「なんだこれ!」
「いや、ただのアップルパイだろう」
シナモンが見つからなくて、自分としては少し物足りない味だった。
何よりシナモンが無いせいで、カスタードの味が強く感じられてとにかく甘い。
砂糖を減らすべきだったとストレートの紅茶で中和しながら食べてる横で、ユーリの顔がおそろしくにやけていることに気が付いた。
あの時は本気で心配したものだ。
何か、体に合わないものを食べさせてしまったんじゃないかと。
「まるで、猫にまたたび、みたいな顔だった」
「・・・猫はそっちだろ」
全くの杞憂だった。
思い出しながら、アップルパイを食べていたユーリの表情をそう表現すれば、ピシッとフォークの先を向けられる。
その右手に持っている皿の上は、空。
「え、もう食った?」
「ああ」
当然、といった顔をしている。
自分の手元の皿の上には、まだ半分ほども残っている。
過去の回想でそんなにぼんやりしていただろうか。
見下ろす自分の皿の上に、すっとフォークの先が伸びる。
ぐさり。
「・・おいっ!」
さすがにそれは無いだろうと、つい皿を手前に引いてしまう。
「うおっ」
取り落としそうになったガトーショコラに、ユーリが慌てて体勢を崩す。
引き寄せた皿と一緒に、刺したフォークごとユーリの体がこちらに傾ぐ。
「ちょっ・・」
足を引っ掛けたユーリの座っていた椅子が、派手な音を立てて床に転がった。
だが、こちらはそれを気にするどころではない。
「・・・・・」
「・・・・・どけ」
何とか落とすことを回避できたガトーショコラは、自分の視界の端で無事皿の上に残っている。
それ以外の視界が暗い。
主に、黒い。
倒れまいと伸ばされたユーリの、フォークを持つ手とは逆の右手が背後の壁まで届いて良かったと、取り合えずそう思う。
そうでもなければ、椅子ごと床に転倒。
椅子の背か床に後頭部を強打することはもちろん、ガトーショコラの生存率は限りなくゼロだっただろう。
そうならなかった事に安堵の息を漏らす。
後は目の前の相手が退いてくれれば良いのだが。
「おい・・?」
微動だにしない相手に訝しげな声が漏れる。
目の前にユーリの上半身があって、本当に何でこいついつもこんなに胸元開けたがるんだろうと場違いなことを思う。
・・露出狂?
思わずついてしまった右手の平の先が、布地で良かった。
男子が女子の胸元を間違えて触ってしまった!キャー!ってなハプニングとは間逆のパターンだが、頭上の相手は悲鳴はおろか無反応。
見上げても黒い髪と、顎先が見えるだけで顔が見えない。
「聞いてるのか、ユーリ。ど・・」
「良い匂いがする」
「は?」
ボソリと頭上で呟かれた言葉。
何でも良いからとにかくどけと押しのけようとした、フォークを掴んだままの片手が捕まれる。
「ん?」
ぐいっ。
ぶんぶん。
ぐぐぐ。
振り払おうとした手首にかかる相手の手の握力が増す。
何故だ。
「甘い、良い匂いがする」
「!!っお菓子作ってたからじゃないかな、ユーリどけっ」
背筋がぞわぞわする。
鼻先でフードを落とそうとするんじゃない!
人の頭に鼻を埋めるな耳に頬ずりするな耳の中に息を吹きかけるなっっっ!
どごっ
「っぐ?!」
一度下げた頭を思い切り打ち上げた。
「いきなり、何しやがる・・・」
「それはこっちのセリフ」
後ろによろめきつつ鼻を片手でかばうユーリの顔が険しい。
だがそんなもんは知ったこっちゃ無い。
ユーリが手を離したフォークが、ガトーショコラに突き刺さったままだ。
構わずそのフォークを掴んで、もぐりと残りを食べた。
「あっ!おい」
何だか急にしょげた様子の相手を横目で見つつ、今度こそ完食する。
おい、も何もこれは元から私の分。
もっとゆっくり味わって食べたかったのに、散々だ。
「・・もうユーリとは一緒に食わん」
相手の空いてる皿を自分のところに重ねて、2本のフォークを添える。
叱られて決まり悪げにふてくされたような顔なんかしたって、可愛くもなんともない。
なんせ、20の男だ。
残りのミルクチョコもずずっと飲み干して、マグカップの取っ手と共にリキュールも持ち上げた。
「・・悪かった」
振り向かずに部屋を出た。
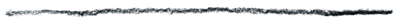
酒場も静かになる真夜中。
街の明かりが消えても、空は相変わらず少しうるさいくらいの明るさを保っている。
相も変わらず、今夜も今夜とて屋根の上に上がって寝そべっていた。
「・・・・・」
夜風が火照った頬に涼しく感じる。
行儀が悪いと思いながらも、寝そべったまま手元のグラスを呷る。
少し温まったミルクとチョコが口の中で溶けて消える。
ふわり、と。
それとは別の甘い匂いが、微かに風に乗って運ばれてきた。
寝そべっていた体をずりずりと動かして、屋根の縁から下を覗き込む。
「!!」
「・・・よお」
覗き込んだタイミングで部屋の窓が開き、人の顔が覗いた。
目が合う。
ちょっと罰の悪そうな顔をした相手は、一瞬そらした瞳をまたこちらに向けてくる。
「降りて来いよ」
「・・・・・」
どうしようかと迷う鼻先に、さっきの甘い匂いがまたふわっと香る。
きょとりと瞬きして空気の中のその甘さを嗅ぐ。
「気になるんだろ。ほら、降りて来い」
次に目が合えば、その暗色の瞳が柔らかく細められた。
無言で屋根の上に乗せていたリキュールと牛乳の入ったビンとグラスを手渡す。
「・・お前、上で一人で飲んでたのかよ」
「今日は涼しいから。それに星が綺麗だ」
「ふうん」
夜空をちらと見上げてから、いつもどおりじゃねえかと呟く頭が窓の中に引っ込む。
・・確かに、ここに来て見上げる夜空はそう変わらない。
それでもふとそう言ってしまうほどには、まだ見慣れてはいないからかもしれない。
「」
もう一度見上げていれば、また名前を呼ばれる。
屋根の縁を掴んで、部屋の中へと滑り込んだ。
「ほら、やる」
「え」
眼前にずずいと差し出されたそれに、思わず目が点になる。
ふんわりと甘い匂いを漂わせるそれは、ふわふわふかふかのきつね色。
四角かったはずのバターは形を無くし、その上からかけられたとろりと艶を帯びたメープルソースに覆われている。
オマケにと真っ白のホイップクリームが添えられたそれは、紛うことなきホットケーキだった。
「え?」
何故にホットケーキ。
つい、窓の外を見てしまう。
真夜中だ。
何故に、真夜中にホットケーキ?
しかも、バターも溶ける暖かさと香りからして出来たてだ。
「腹が減って、ちょっと夜食代わりに作ったんだよ。・・いらねえか?」
「いる」
さすが、甘党。
夜食にホットケーキなんて、世のお嬢さんが聞いたら拳をわなわなと震わせるに違いない。
世のお嬢さんという枠には入らない自分は、ちょっと引かれた皿を結局掴んでしまった。
ユーリの瞳がふっと笑った。
「っていうのは、まあ冗談だ」
「?え?」
受け取った皿の上の実に美味しそうなホットケーキと、相手の顔を交互に見比べる。
期待だけさせて、食べるなと?
そう思わず顔に浮かべてしまっていたのだろう。
「いや、そっちじゃねえよ。それは、やる。そうじゃなくって、さすがに俺も夜食にホットケーキは食わねえよ」
苦笑する相手に、じゃあ何でこんな時分に作ったんだと思いつつ、早くその手のフォークをくれとつい目でちらちらと見てしまう。
「ガトーショコラ、美味いもん食わせてくれただろ。なのに、あんな顔させちまったと思って・・・悪かった。これは詫びの品だ」
「だからって、こんな時間に・・」
「夕食後から姿が見えなくて、渡すタイミングを逃したんだよ。まさか屋根の上で酒盛りしてるとは思わなかったけどな」
「・・・飲むか?」
目の前でとぷんと酒を揺らしてみせる。
ユーリは笑って頷いた。
「ご相伴に預からせてもらうとするか」
真夜中にホットケーキを肴に甘い酒を飲むなんて。
「今夜は、贅沢な夜だ」
見上げた夜空の中で、凛々の明星がチカリと瞬いた。
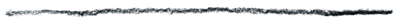
・・・。
・・・・・・。
・・・・・・・・。
・・・・・・・・・・重い。
「おい」
ゆさゆさ。
「おい・・ユーリ」
「・・・んー・・」
んー、じゃない。
「重い、どけ」
「・・・んー」
いつの間に寝てしまっていたのか。
仰向けで目を覚ませば、隣に寝そべっていたユーリにヘッドロックされている。
首に腕の重みがかかって息苦しくて目が覚めたようだ。
ごそごそと頭上で動く音がする。
それはやがてまた静かになった。
・・静かに、寝息を立てている。
人の耳元で。
「耳に息を当てるな、離れろ」
「・・・・・」
「ユーリっ!」
ゴス
「~~~っ痛え!」
肘を背後に打ち出した。
自分の発した声と肘から伝わる振動で、頭蓋の中がぐわんぐわんとシェイクされる。
思わず頭を抱えた。
これは飲みすぎたかもしれない。
その横で、やっと上半身を起こした相手はわき腹を押さえている。
うな垂れた顔に、長い黒髪がかかってその隙間から恨みがましい紫がかった黒い目が覗いている。
「朝から何してくれてんだよ・・いってえ・・」
「それは・・こっちのセリフ・・」
低い低い声に、呻き声で応える。
そしてやっと気が付いた。
リキュールの瓶がベッドの足元に転がっていることに。
栓もされてない瓶からこぼれるものはない。
それの指すところはつまり。
「え。空っぽ・・?」
甘いチョコレートの香りが漂う中に、くらりと酩酊しそうなアルコールの匂いが混じっている。
明け方の爽やかな風が頑張ってくれれば、もう少しましな空気になる かもしれない。
「いつの間に全部飲んでたんだ・・?」
呆然としていれば背後から不穏な気配を感じる。
慌ててベッドから降りようとした体が、後方に引き寄せられた。
「っ!・・おいっ」
「なあ、もうちっとこのまま」
胴に回された腕が、寝起きとは思えない力を発揮している。
起きたと思ったがまだ寝ぼけてるんじゃないのか。
振り向いて抗議しようと目元に、黒い帳が下りる。
ぎょっとして見上げた視線の先、闇の中に暗い夜空色をした瞳がこちらを覗きこんでいる。
「・・いいだろ」
いいわけあるかと答える前に、その顔がすっと背後に引いて。
「!!!っっん」
ぞくりとした震えが背筋を駆け上がる。
離れようと頭を振れば胴に回されていた片腕が解かれ、その間に逃げ出そうと前のめりになった顔に離れたほうの手が伸ばされる。
目の前が暗闇に包まれた。
片手で目元が覆われるのと同時に、親指と人差し指に力が込められて背後に引き戻される。
「おいっ・・悪戯が過ぎる・・・ぁ!」
耳の先を口に含んで甘噛みされて、堪えきれずに声が出てしまう。
背後からふっと笑い声が漏れて、その微かな吐息にも耳朶が震えてしまう。
視界が利かない分、聴覚と触覚が敏感になっている。
逃げ出そうと身じろぎすれば、こちらの両腕ごと胴を拘束する腕に更に力が込められた。
「ユーリっ!」
「イイ声出す方が悪い」
湿ったものが耳の内側を這う。
否応なしにひくりと反応を返してしまう体が恨めしい。
背後にぴたりとくっついている相手には、その反応が如実に伝わってしまっていることだろう。
背中とくっついているユーリの体が時折小刻みに揺れているのは、笑っているからだと分かる。
「本当に弱いんだな、耳」
そう耳元で囁いて、息を吹きかけるこの男は本当に性質が悪い。
「~~~~っっ!」
ぐわっと体内の熱が上がる。。
お酒をそれなりに飲んで、まだ少し酔いが残ってる起き抜けにされるそれはたまったもんじゃない。
一気に血の気が上って顔も背中も熱い。
自分の体が熱いのか、背後のユーリからのものなのかも分からない。
取り合えず思うことは。
「本当・・朝っぱらから、何・・してくれてんだっっ」
血がめぐって更にがんがんと痛み出す頭を、何とか少しだけ下に下げてから打ち上げた。
脳天に衝撃が走る。
意味を成さない呻き声が聞こえたから、舌でも噛んだのかもしれないが、こっちもこっちで眩暈がしそうだ。
解放された両手で頭を抱える。
ああ、本当に朝から何してるんだ・・。
よろめきながら何とか床に降り立って、背後からの声を無視して隣の部屋の扉を開ける。
閉める、鍵をかける、ベッドに倒れこむ。
「・・・弱いんじゃないか・・」
酒は飲んでも飲まれるな。
そうは見えなかったが、酔っていたようだ。
性質が悪い酔い方をする相手を見て、二度と一緒に酒は飲まん、と思うと同時に思考回路はぷつんと切れた。
◆アトガキ
2013.10.3
まだ、ふわふわしております。
はー。
何か微妙テイストですね。
1つ言えることは、そんなんしたら口の中毛だらけになるよ!ってことですかね。。。
icon by Rose Fever
background & line by ヒバナ
