一
「♪♪」
「あら、おじさま楽しそうね。何か良いことでもあったのかしら?」
何やら楽しげなレイヴンの姿に通りすがりのジュディスが声をかければ、嬉しそうな声を上げてちょいちょいと片手で招かれる。
企みごとをしているその顔に薄く微笑んで近づけば、相手は口元に片手を添えて少し辺りを憚るように声を落とした。
「ジュディスちゃん!ねぇねぇ、セーネンの拗ねた顔って、可愛いと思わなーい?」
「おじさまったら、いつの間にそういう趣味になったの?妬けちゃうわね」
「違うわよっ」
お互い分かっているやり取りを楽しみつつ促せば、レイヴン曰く、自由行動中にお姫様が美味しそうなお菓子を見つけて買ってきて、宿屋で合流したリタとカロル、と食べていたと。
最後の一口をが口にしたときに丁度ラピードと一緒にユーリが帰って来て。
「・・・俺の分はねーのかよ・・・ってぼそっと言ってねえ」
一瞬声音を低く真似して、その後またくすくすと笑い出す。
よっぽど楽しかったらしい。
でもそれは確かにちょっと意外だった。
「がいるからかしらね」
「やっぱり?やっぱりジュデスちゃんもそう思う?下町で過ごした仲だっていうものね」
そう言えば、納得するかのように顎に手を当ててレイヴンはしみじみと呟く。
旅をする間、ユーリは一歩離れた保護者的な立ち位置を取ろうとすることが多い。
メンバーが年下なこともあるし、何だかんだ言って頼みごとを聞いたり、面倒を引き受けているうちにそう言うスタンスに収まってしまったのだろう。
あまり誰かに頼ることも無く、やれる時は出来るだけ自分でやってしまおうとするけれど、年下の彼らが何かをしようとする時は、やり過ぎない程度に手を貸してさり気なく見守っている。
「もしその中にがいなかったら、顔にも出さなかったでしょうに」
思わず表情に出してしまった上に、レイヴンにしっかり見られてしまったことが知れたら、きっと彼は罰が悪そうな顔をするだろう。
それを思えば、ジュディスの顔にも自然と笑みが広がる。
こちらの顔を見て、レイヴンは何を思ったのかぴんと人差し指を上げた。
「ねえねえ、ジュディスちゃん?・・・・」
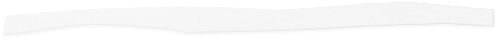
「ちゃんっ」
かけられた声に宿屋の廊下を歩いていた足を止める。
廊下の端から、派手な服の袖がちょいちょいと手招きをしていた。
ぼさぼさっとした髪をひとくくりしているその相手は確か。
「レイヴン?どうかした?」
「いーいところに!」
上機嫌なその表情に、一瞬向かいかけた足を止めたくなる。
何だろう。
厄介ごとの匂いがするというか、嫌な予感?
あまり、近づきたくないなあどうしようと逡巡する。
「ちょっと、どうしてそこで止まるのよ」
「いや・・・なんとなく」
「もうおじさまったら、駄目ね。・・」
「ジュディスまで。そんなところで二人でこそこそ何してる・・?」
むっとした顔のレイヴンの後ろから、ジュディスが顔を出してその手で優雅にまた手招きされる。
呆れた溜息を吐きながらも仕方なく招かれてみれば、レイヴンは更にいじけ出した。
「おっさんが呼んでも来てくれないのに、ジュディスちゃんが呼んだらあっさり来るなんて・・・」
「・・・で?どした??」
膝を抱えて廊下の端に座り込むその頭を横目で見下ろしつつ、青い髪のいつ見ても素敵なプロポーションのもう一人の相手に話を促す。
「ねえ、。ユーリから聞いたのだけれど、あなたもお菓子作りが得意なんですって?」
「得意というほどでは無いけれど」
答えつつ頷けば、クリティア族というらしい彼女の長い触角がふわりと揺れる。
首を傾げたジュディスは、足元で尚もいじけたままのレイヴンを見下ろして、仕方が無さそうに苦笑する。
「おじさまが、ええと何だったかしら・・・カシワ?」
レイヴンの肩に手を添えて、思い出そうとするジュディスにレイヴンがようやく顔を上げる。
「ちゃん、柏餅って知ってるかしら?」
その顔に先ほどまでいじけていた様子は無い。
立ち上がった目線が同じくらいの相手に、頷き返す。
「知ってるよ。柏の葉で餡子をはさんだ餅を包んだお菓子だよね」
「そーう、それよ!おっさん、今それが無性に食べたくなっちゃって!」
「そりゃまた急な・・・」
でも何で急に?と聞き返せば、無言でその目が逸らされた。
仕方が無いので、隣に立つジュディスにも目で聞いてみる。
「お姫様が、街で美味しいものを買ってきたそうだけれど、おじさまはほら甘いものが苦手でしょう?」
「ああ、私ももらった。甘くて美味しかったけれど・・そうか、レイヴンは食べられなかったか」
「それで、そのカシワモチって言うのかしら?それには甘いものとそうでないものもあるって言うのよ。・・もし良ければ、作ってあげてくれないかしら?」
「それは、まあ材料があれば構わないけれど・・・」
「!本当?ちゃんったら、おっさんもう感激っ」
両手を広げて飛び掛ってきそうな相手から、そっと距離をとって頷く。
「んじゃ、レイヴン用に味噌餡のものと、他のみんなは普通に餡子で作ればいいのかな。んじゃちょっと買いに行ってくる」
「待って、ちゃん、おっさんも一緒に!」
「二人とも、行ってらっしゃい」
笑顔で手を振るジュディスに手を振り返し、にこにこと上機嫌なレイヴンを連れて柏餅の材料を買いに街に出た。
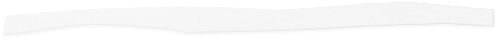
「それで?何でいきなり柏餅?」
羽織の中に手を突っ込んでひょこひょこと、その名前に似た動作で街中を歩く連れを見て話しかける。
その顔が、きょとんとこちらを見返す。
「え、おっさんもたまには一緒に美味しいもの食べる輪に入りたいなぁ、なんて・・」
「ふうん」
「・・・・・」
「・・・・・」
「・・・えっと」
袖に突っ込んでいた両手を出して、そっと窺うようにこちらを見てくる。
何かあるだろうとは思っていたが、柏餅を作ることには別に何も問題は無い。
「いや、言わなくていいよ」
「えー・・そう言われちゃうと何だか」
困ったように眉を下げる相手に、首を傾げる。
「どうせ、たいした理由じゃ無さそうだ」
「自分で聞いておいてひどい!!・・そんな、ばっさり切られるとおっさん、傷つくわ」
ガラスのハートが・・と胸元を押さえている。
レイヴンを置いて店内を見回して、必要なものを揃えていく。
「そんなことより」
「・・そんなこと・・」
いちいちいじけるのを相手するのも面倒で放置する。
これがエステリーゼなら、きっと親身になって相手をするのだろう。
他の面子は・・おそらく自分と同じく放置するような気がする。
エステリーゼは良い子だなとしみじみ思う。
さっきも、街で見かけたお菓子をみなさんで食べようと思って買ってきました!と、リタと仲良く帰ってきて手に持っていた一口サイズの揚げ菓子を振舞ってくれた。
レモンと香草が練りこんである独特な風合いと、甘い蜂蜜がからまって確かに美味しかった。
ついついお言葉に甘えて手を伸ばし、気が付けば最後の1つを口に放り込んでしまっていて。
丁度帰ってきたユーリの、あの微妙な顔と言ったら。
「柏の葉は無さそうだから、何か似たような大きめの葉で代用するけども、それでいいかな?」
「・・・いいわよー」
「ちゃんと甘すぎない味噌餡で作るから、そんないじけるな」
言って、帰るぞとその丸まった背をぺしぺし叩く。
ちょっと期待をこめた目に笑い返して、宿屋への道をまた戻る。
ユーリには逆に甘めの餡子をたっぷり詰め込んであげようと思う。
さっきのエステルのお土産を食べてしまったお詫びだ。
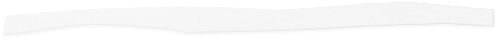
宿の厨房を一部貸してもらい買ってきた餡子を取り出して、白餡には白味噌を混ぜ合わせる。
出来た味噌餡と漉し餡を、適度な大きさに丸めて皿に並べておく。
餡子も作らないと駄目かと思っていたが、レイヴンが売ってるお店に連れて行ってくれた。
せんべいといい、こっちの世界では珍しい方の食べ物を良く知っているなと思う。
粉と砂糖、塩をボールの中で混ぜ合わせたところに熱湯を加えてこねる。
指先が赤くなって、視界が水蒸気でけぶる。
「・・・あち」
ちょいちょいと指を入れてこねて、熱くなりすぎたと感じたら隣の冷水に指を浸して、そしてまた熱湯と格闘する。
徐々に熱さに慣れた頃に、生地はやっと耳たぶくらいの硬さになった。
とはいっても、耳たぶの柔らかさが自分と人では違うので、おそらくこのくらい、といった程度で。
「・・?こんなところで何やってんだ?」
「お、いいところに」
湯気がもわっと漂う厨房の一角に黒い人影が入ってくる。
ごつごつとした特徴的なブーツの足音から誰が来たか分かっていたので、振り返らずに手招きをすれば何をしているのか興味を惹かれた様子の相手が横に立つ。
その長い髪の間に覗く耳たぶを、指先でちょいっと摘んだ。
「!あつっ・・って何でこんな熱いんだよっ」
「・・・こんなもんか」
隣で慌てたような声を上げる相手を無視して、適当にちぎってまるめた生地を蒸し器に並べて蓋をして火をつける。
その直後に手をとられて、流水の中にバシャッとつっこまれた。
「何作ってんだか知らねえけど、火傷してんじゃねえか」
「これくらいは平気」
言い返しながらも蒸している間は他にやることが無いので、されるがままにしていれば指先を浸していた片手が離れ、濡れたその手に頬を抓まれる。
ピトリと冷たい指先に触れられて思わず眉根を寄せて見上げれば、それ以上にしかめっ面の相手と目が合った。
「・・・・・」
「・・・・・」
お互い、相手の言葉が分かっているので、何も言わないままにらみ合いが続く。
自分はこれくらい問題ないと思うのだが、ユーリはそうは思ってはいないのだろう。
本当に平気なのになと思いつつもう十分に冷えた指先を水から離せば、ユーリの手は離れていった。
「・・・悪かった。気を遣わせた」
「!!そうじゃ無くってだな・・」
一言告げて、蒸し器へと視線を逸らせばユーリは苦虫を飲み込んだような顔をした。
怪我をしたんじゃないかと心配をしてくれたのは分かっている。
それでも、何となく素直に礼は言えない。
何故だろう。
時折、こういった気分になる。
そういう気遣われ方をされるとむず痒いというか、やけに抵抗感がある。
この気遣い方はエステリーゼやリタ、ジュディスにやってあげれば良くて、自分のことは放っておいてくれて良いのに。
無言で立つユーリには申し訳ないと思いつつも、蒸し器を覗いて頃合かとその中身を取り出して作業を続けた。
「・・・で、それは何なんだ?」
この会話を続けることは諦めたらしい、溜息をついて腰に手を当ててボールの中を覗き込んでユーリが問う。
取り出した生地をすりこ木でついてこねる。
「柏餅が食べたいってレイヴンからリクエストがあって」
「カシワモチ?・・へえ」
ふんわりもっちりとしてきた生地に興味津々の顔をするユーリに感謝する。
きっとさっきの会話を続けていても、お互い平行線を辿っていただろう。
早々と切り上げてくれたことは有難かった。
こねた生地を冷水に浸して、冷えてしまわないうちに水から引き上げて再度手でこねる。
「・・・しょっぱ」
「こら、つまみ食いするな」
皿に並べておいた味噌餡をなめたらしい、微妙な顔をしているユーリをたしなめる。
「そっちはレイヴン用の味噌餡で、ユーリや他のみんなにはそっちの色が濃い漉し餡の方」
「・・ふーん」
「・・・・・」
一瞬またこねる生地に目を向けた間に、さっと動く気配がする。
ちらっと目を向ければ、すっとその視線がそらされる。
この青年は、出来上がるまで待てないのだろうか。
「・・・・美味しかったか?」
「・・・甘いな」
その嬉しそうな顔を見れば、甘さは十分だったらしい。
レイヴンの味噌餡はもうつまみ食いはしないだろうし、ユーリへの詫びも込めてある以上、もはや注意する気も起きない。
もちもちの生地を人数分に分けて、一つ一つに餡をはさんで閉じていく。
最後に柏代わりの大判の葉で包めば出来上がりだ。
「ん?数が合わなくねえか?」
片方の皿を持ち上げたユーリが数を数えて首を傾げる。
「餡子をつまみ食いした誰かさんがいるからな」
「・・・悪かったっての」
「冗談だ」
素直に謝る相手に笑いを零して、首を振る。
「他にもちょっと作りたくてな、だからそれは先に持ってってみんなで食べてて良い」
自分の分は無し。
だから数は1人2つで、合計12個の柏餅が皿に並んでいた。
出来たてのうちにとその背を押せば、何か言いたそうにしながらもユーリは皿を持って厨房を出て行った。
「・・・さて」
小さな鍋を用意して、取り出したるは醤油とみりんと砂糖と片栗粉。
残った餅の生地を一口サイズにころころと転がして皿に並べてから、材料を鍋に入れてかき混ぜる。
漂う甘辛い匂いに、の頬も自然と緩む。
とろりと琥珀色に照り輝くタレをかければ出来上がり。
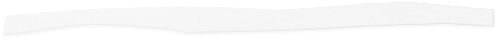
借りた厨房をささっと手早く片付けて、宿屋の人にお礼を言ってから皿を持って部屋に戻る。
みんなが集まっているだろう部屋の扉を開けて。
「・・・・どしたよ」
の目は点になった。
「あっ、!」
「、あのカシワモチ?美味しかったです!・・あの、」
カロルの声と、両手を組んで目を輝かせて立ち上がったエステリーゼに目を向けるも、一瞬後にその表情が曇って部屋の一角をちらと見て何やら言いにくそうにしている。
その横でリタは椅子に座って、我関せずとばかりにもぐもぐと口を動かしている。
「リタ、美味い?」
「・・・美味しかったわよ、ごちそうさま」
素っ気無い返事だが、ちらとこちらを見て逸らされた顔が少し赤いので、照れ隠しだと分かる。
自分に柏餅を依頼してきたジュディスも、美味しかったわと微笑んでいる。
それは良かったと返しつつ、エステリーゼがさっきからちらちらと心配そうに見ている方へ目を向けた。
そう、問題はその一角だ。
「二人とも、仲良くお菓子も食べられないのか・・・」
ひとしきり彼らを眺めて、呆れて皿をテーブルに置いて腰に手を当てる。
しれっとしているリタや、慌てるカロルやエステリーゼの前で、大人気ない大人が二匹。
ラピードなんて、飽きた様子で欠伸をしているくらいだ。
「だってセーネンが食べないから、これも味噌餡なんだとてっきり!」
「数よく見て食えよおっさん・・・?」
漉し餡入りの柏餅を食べたのかげっそりとした顔をしたレイヴンの米神に、ぐりぐりと両拳をめり込ませたユーリが低い声を出している。
その言葉を聞いて、には何となく事の次第が分かった。
おそらくユーリは、数が合わなかったため自分の分を残しておいてくれたのだろう。
割り当てられた2つの内の1つを皿に残していたら、それを勘違いしたレイヴンが食べてしまった、と。
「ふふっ、おじさまったら」
駄目ねとくすくすとジュディスが笑ってそれを見ている。
分かっていたなら止めてくれれば良かったのに、と思えど起こってしまったことはもう仕方が無い。
「ユーリ、レイヴンを離してやれ。ほれ、追加のみたらしだんごもあるから」
「・・・・・」
「セーネンってば、悪かったわよ~・・・!」
「ほら、レイヴンも謝ってることだし。私はみたらし食べられれば良い」
むすっとした顔でレイヴンを解放して、ユーリは椅子にどかっと腰をかけた。
解放されたレイヴンは色んな意味でダメージを負って、青い顔をして呻いている。
「大丈夫か、レイヴン?」
「大丈夫じゃないわよー・・でもみたらしは食べる」
レイヴンがよろよろと手をのばした竹串の先のみたらしを、ユーリが先に刺してぽいっと口に投げ込んだ。
あー!とかうう・・とか言った声を漏らして、恨みがましくレイヴンはユーリを見上げている。
全くこの年長者どもは、よくもこうくだらないことで騒げるものだ。
呆れた目で見ていれば、ユーリの瞳がこちらを見た。
もぐもぐ、ごくんと飲み込んで次のみたらしに手を伸ばす。
「・・・ほら」
「・・・え?」
てっきり自分で食べるものだと思っていれば、先にみたらしを刺した竹串を差し出される。
「早く食わねえと、またこの食い意地張ったおっさんに全部食われちまうだろ」
「セーネン・・ひどい」
「ほら」
レイヴンの訴えを無視して、更にずずいと近づけてくるみたらしに、思わず仰け反ってしまう。
「いや、自分で食べるから」
このみたらしは自分で食えと続けようとすれば、その眼光が急に鋭くなる。
え?
何でいきなりそんな魔王様みたいなオーラを放っていらっしゃる・・?
「あら」
ジュディスのあげた、あらあらまあまあといった感じの声に言葉に詰まる。
ほら見ろ、余計なことするからと眉間にしわを寄せてみても、竹串が下げられる気配は無い。
ちらと横目で見た部屋の中、エステリーゼの何故かきらきらした瞳が視界に入る。
そんな純粋な瞳で見られても、困る。
乙女的な展開だろうが何だろうが、こういうのは本当に困る。
これ以上何か言われる前にとユーリの目に無言で訴えるが、椅子から身を乗り出した相手は仰け反った距離を更に詰めてきた。
声に出さずとも、早く口を開けないとこのまま突っ込むぞといった圧力をひしひしと感じる。
「~~~!」
もぐ。
脅しに、屈してしまった・・・。
殺傷能力がありそうな目で竹串を持つなと言いたい。
みたらしで喉をつまらせるのもごめんだし、竹串が喉に刺さったら流血大惨事だ。
まあ、そんなことにはならないだろうとは思うのだが。
みたらしを引き抜いた竹串をユーリの手ごと押し返せば、それはすんなりと離れていった。
そのままの姿勢で惰性で咀嚼する。
「・・・・・・」
「これ、美味いな」
大人しく食べたことに、細められた目と弧を描く口元。
一転して満足げに笑う相手に、一体お前は何をしたいんだと脱力する。
飲み込む。
おかげでこっちは味わう余裕が無い。
「それは・・何より・・・」
疲労感が半端無い。
辺りを恐る恐る見渡せば。
机の端でやっとありつけたみたらしを堪能しつつ、さりげなくこちらを見ているレイヴン。
にっこりと微笑むジュディス。
赤い頬に手を添えているエステリーゼ。
視線が宙をさ迷っているカロル。
「・・・馬鹿っぽい」
そうだね、リタ。
自分でもそう思う。
謎の空気のままみたらしも食べ終えて、何とかまったりした空気の中。
「・・で?何ではいきなりカシワモチを作ることになったんだ?」
美味かったけど、とユーリが首を傾げる。
「ああ、何かレイヴンが・・」
「おっさん?」
「あ!うん、そ、そうなのよ!ちょっと急に食べたいなーなんて」
ちらりと向けられたユーリの視線に、何故かどもっているレイヴンにも首を傾げる。
さっきもそんな反応をしていたし、思えば廊下の端で呼び止められた時から、何だか怪しげな態度だった。
買い物に行く途中で話していた時は、レシピを思い出していたこともあって聞かなくてもいっかと思っていたのだが、食べ終えて手持ち無沙汰になってしまった今は気になる気持ちもある。
「そういやレイヴンはどこでこういう食べ物のことを知ったの?」
「え?あ、えっとそれはその・・」
言いよどむ相手に、そういやレイヴンの素性って本当に良く分からないなと改めて思う。
でもそれは、自分も同じことで。
「いや、言いたくないなら別に言わなくても良い」
「・・・ええっと」
「ただ、お互い同じ食べ物知ってたってことに、驚いただけ」
「・・そうね」
にこりと笑えば、レイヴンの強張っていた顔も少し緩む。
懐かしい味、とかなのだろうか。
「美味しかった?」
「!!そりゃあもう、あの甘すぎない絶妙な味噌餡の美味しさったら。おっさんの我がままを聞いてくれてありがとうね、ちゃん」
「喜んでくれたのなら、良いよ」
その横でどことなく納得がいっていない顔をしているユーリに顔を向ける。
「ユーリ」
「・・・ん?」
「エステリーゼの買ってきてくれたお土産、食べちゃったから。そのお詫びも込めてあったんだ」
「へ?」
言われた相手はきょとんとしている。
思い出そうとしているユーリの横で、レイヴンが不意に声を上げた。
「そう、それなのよっ」
言ってから、あっとその口を覆う。
その、やっちゃったという顔に自分とユーリの目線が向かう。
「それって・・・なんだよ、おっさん」
「・・レイヴン?」
周りのメンバーがよく分からないといった顔をしている中で、ジュディスだけがにこにことした様子を崩さない。
「ジュディスは何か知っている?」
「何のことかしら?」
鉄壁の微笑を崩さない相手に、これは知ってても言わないだろうと分かる。
ならば、と再度目線の向かう先、逃げ出しそうなレイヴンの肩をユーリが掴む。
意地が悪そうな顔をしてレイヴンに圧力をかけるユーリを見て、ご愁傷様と心の中で合掌する。
「レイヴン、諦めろ」
「諦めろって、・・ちゃん?」
「その顔をしたユーリの追求の魔の手からは、逃げ出す以外の術は無い」
首を振って、諦めろと諭す。
捕まる前に逃げ出せたなら良かっただろうに。
口元だけ笑みを見せた迫力の魔王様ことユーリによって、過去幾度と無く隠し事を吐けと脅された経験を思い出す。
何を言っても、どうかわそうとしても、何故だかすぐに否定される。
違う、そうじゃないだろう?と笑顔の脅迫だ。
魔王モードのユーリには、読心術が使えるんじゃなかろうか。
魔法は使えないといっていたが、あれは嘘だと思う。
「んで、おっさん。エステルの土産のことで、何か言いたいことでもあったのか?」
「いや、無い無い、何もありませ・・ぐえ」
「観念して、全部吐いちまえよ」
「ギ、ギブギブ・・!」
「ユーリ、そのままだとレイヴンが物理的に何かを吐いてしまいそうだ」
「その前に素直に話せば良いってこった」
「鬼っ」
「・・くだらない・・私、先に部屋に戻ってるわね」
「あ、リタ、待ってください!」
往生際の悪いレイヴンと魔王ユーリの膠着状態が続いて、一人、また一人と部屋から人がいなくなる。
「えっと、僕ちょっと散歩にいってくる」
カロルの開けた扉の隙間から、ラピードが出て行って残るは4名。
どうしたもんかと眺めていれば、隣に黙って座っていたジュディスが不意に笑った。
「ジュディ・・・」
やっぱ何か知ってるだろ、とレイヴンを締め上げつつユーリの目がジュディスを捉える。
「あら、怖いわ」
ジュディスの緋色の瞳がレイヴンの方をちらと見る。
「そうね・・・・?」
「え?・・・何、ジュディス?」
一瞬、何事かを考えて揺らいだジュディスの瞳がこちらを向いて、名前を呼ばれる。
このタイミングで呼ばれるような理由はあっただろうか。
思いつかなくて聞き返せば、薄っすらと瞳を細めて微笑まれる。
年下とは思えない妖艶な笑みだが、裏で何を考えているのかが分からなくて、少し逃げ腰になる。
「あらやだ、そんな逃げなくても。ただ、ちょっと聞きたいことがあっただけなの」
「聞きたいこと?」
ええ、と頷かれる。
ユーリと視線が合って、お互いに首を傾げ合ってしまった。
レイヴンはやっと解放されて、その横で咳き込んでいる。
「私たちが知らないお菓子を、あなたとレイヴンだけが知っていた・・」
「ああ、それは」
「二人とも、故郷が同じ・・とかなのかしらって」
それは私も不思議だなと思っていた、という前にジュディスが続ける。
思わず目が点になった。
いやいやそれは無いだろうと思いつつ、そんなことってありうるのだろうかと今度はレイヴンと目を見合わせてしまう。
向こうも驚いたような目でこちらを見ている。
「それは・・・」
「えっとジュディス、それはたぶん無い・・」
「あら、どうしてそう言いきれるのかしら?」
「いや、どうしてっていうか・・」
アメストリスから来ましたと言って、どうする。
フードの下のこともまだ言えていない。
何か理由があるのだろうと察してくれてか誰も聞いては来ないけれど、1つ話せば全てを話すことに繋がる。
まだ、もう少し待って欲しいな、なんて自分らしくも無くずるずると先延ばしにしてしまっている。
どうすべきか。
「・・・・・・ええと」
うろうろと無意味に部屋の中に視線をうろつかせば、何故か不機嫌な顔をしたユーリが目に留まる。
いや、ユーリには少しだけ話したからそんな顔をする意味が分からない。
レイヴンと故郷が違うってことぐらい分かるだろうが。
「・・おっさんと」
「ユーリ?」
「こんな瀕死のおっさんとが同じ故郷なわけねーだろ」
「ひど!そのとおりだけどセーネン、もうちょっと言葉を・・」
「そうだろ、」
「あ、ああうん」
「あら、ユーリには聞いてないのだけれど」
どことなく楽しげな顔をしたジュディスの名前を、ユーリが呼ぶ。
「お前らしくねーんじゃねえの?」
「ふふ、そうかもしれないわね」
細めあった瞳。
黒紫と緋色が無言で見つめあうのを、当事者のはずなのに何故か傍観する残り二名。
「・・・レイヴン、本当に何?何があって、こんな事態?」
「えっとー、・・ちょっとした、出来心かしら」
しゃがみ込んで足元でこそこそと会話する。
出来心、と言うからにはやはりレイヴンが何か悪戯を思いついて、ジュディスがのったというところだろうか。
巻き込まれた身としては、被害は少なめでお願いしますと言いたかったが、頭上ではすでに龍と虎が向き合っている。
・・いや、狼と龍か?
「・・・何だか知らんけど、言いだしっぺ?・・ほら」
何とかしてくれと脇を肘で突く。
ええ、無理無理!と頭を振って返される。
「おっさんのライフはすでにゼロよ」
ほらほらと、締め上げられた首を示される。
まあ、確かに赤いけれども。
「・・巻き込まれ事故にあったんで、こっちもライフゼロ」
だからほれ、いやいやここは若者に・・・と事態の収拾役を押し付けあってると、頭上に影がかかった。
「おじさまったらいつの間に」
「二人とも、随分と仲がいいな・・?」
思わず、二人で手を握り合ってしまいそうな怖さがそこにはあった。
「おら、そろそろ片付けて寝るぞ」
「いや、うんそうだね・・って何でそこでレイヴンじゃなくて・・待っ」
皿をまとめてひとつに重ねたユーリのもう片方の手に襟首を掴まれる。
フードが外れる!と手で押さえるも力敵わず、ずるずると引きずられる。
部屋の中では、にっこりと微笑むジュディスと力なく手を振るレイヴン。
・・レイヴン!?
「おい、元凶ー!」
「ごめん、ちゃん!この埋め合わせは必ず~」
埋め合わせとかはいいから、今、まさにこの時点での助けを求めているんだけれどという訴えは華麗にスルーされる。
・・・味方は、いないのか・・。
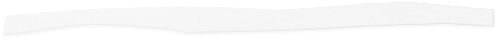
次の日の早朝、レイヴンから事の次第を聞いた。
「・・は?ユーリの拗ねた顔?」
「ちょっ声が大きいって、ちゃん」
「・・・・・」
「本当にごめんもうしないからその汚いようなものを見るような目は止めて・・」
汚いものというよりはもう、ああん?っていう目をしている気がする。
自覚がある。
ユーリの拗ねた顔が見たい?勝手にやっててくれ。
私が作ったお菓子の最後のひとつを食べたら、またそんな顔するんじゃないかって?
結果がアレだった。
本当の本当に巻き込まれただけだったこっちは、それはもう盛大に火傷した。
「だから、悪かったって!もうしませんっ、このとーりっ!」
「・・・・・」
頭上で両手を合わせて、頭を下げられる。
どうしてくれようかと思っていたが、何だかもうその内容の余りのくだらなさにどうでも良くなってきてしまった。
溜息を吐けば、ぼさぼさのひとくくりにされた黒髪が揺れて、そっと上目遣いに様子を窺ってくる。
ひらっと手を振る。
「お詫びに、またあの手のお菓子情報があったら教えて」
「えっ」
「おせんべも分けてもらえると嬉しい」
「!!ちゃんっ」
おっさん感激アタックをかわす。
「もう、つれないんだから!・・あ、そうそう」
「・・・つれない、ね。・・今度は何」
ごそごそと袂から何かを取り出して、はいと手渡される。
中の見えない小さな紙袋をごそごそと覗き込めば。
「!・・・綺麗だな」
「でしょー。お詫びの品。受け取って」
「・・ありがとう」
小瓶に入った小さな色とりどりの星。
つんつんと丸くとがった形の、ころころと甘い・・。
「金平糖なんて、久しぶりだ」
「知ってるんじゃないかなと思ってね」
優しい笑みに促されて、小瓶の封を切る。
片手の平にころりと転がり落ちた星屑を1つ口の中に放り込んだ。
甘い。
「あっ」
「ん?」
不意に声を上げたレイヴンを見上げる。
その視線の先が背後を向いていて、金平糖を口の中で転がしながら振り返る。
「お、ユーリ」
こちらを向いて丸くなっていた紫がかった瞳がすっと細まる。
むっと引き結ばれた口元に、何かあったのだろうかと首を傾げる。
「ごめん、ちゃん」
「え?レイヴンどうした、いきなり」
いきなり耳元でこそっと謝られて、訳も分からず振り向く。
片手を顔の前でぴっと縦に立てるそのポーズは・・・すまん?
「朝っぱらからこんなとこで二人して、何してんだ」
「こんなとこって、宿屋だろ」
「朝っぱらから、宿屋の、裏手、な」
「・・・・・」
やけに「朝っぱら」と「裏手」を強調された。
まあ、こっそり昨日の事の真相を聞いていたからなんだけど。
「まあまあ・・あ、ユーリにもやる」
手を出せと催促して、いぶかしみながらも渋々出した手の平に小瓶を軽く傾ける。
ころりと転がり出たのは、小さな星屑。
「・・何だこれ」
「金平糖っていう飴。甘いよ」
もう片方の指先でつまみ上げてしみじみと眺めている相手に教えれば、ふうんと声が返ってきた。
珍しい。
甘いものには目が無いから、そう教えればさっさと食べてしまうと思ったのに。
指先のそれと持っている小瓶、そしてこちらを見て、最後に背後に目を向ける。
背後に立っているのはレイヴンだ。
つられてまた振り向けば、レイヴンの笑顔が少しひきつっている。
え?あげるの駄目だった?
よく分からない間にすっと歩き出したユーリが、指先に摘んだ金平糖をぐっと突き出した。
「!!むぐっ」
「っ!ユーリ・・?」
何か声を上げようとしたレイヴンの口に金平糖が放り込まれた。
途端にレイヴンの顔が歪む。
「・・・いや、いらないんだったら返してくれれば良かったんだが」
「なんでだろーな、急にいらっとして、つい、な」
さらっと暴言を吐いた気がする。
その手が伸びてきて、小瓶を掴む。
「え?」
ざらっと、傾いた小さな小瓶から星がこぼれた。
・・・ユーリの口の中に。
ぽかんと見ていれば、ん、と小瓶を返される。
って、もう後数粒しか残ってないんだが・・。
もぐもぐじゃりじゃりといった音が聞こえる。
金平糖を頬張ったユーリからだ。
「・・・金平糖・・」
「意外といけるな」
しれっとのたまうその脇腹に膝蹴りを仕掛ける、そんな旅の早朝。
◆アトガキ
2013.10.29
Stop your sulking, honey.
「おいおい、拗ねるなよ」
無駄に長い上に、何がしたかったんだかさっぱり分からない出来に。
そもそも、この訳の言い方なら言うのはユーリで、拗ねるのはヒロイン側であるはずなんですが。
この主人公、そうそう拗ねそうにない。
ここはユーリに拗ねていただこうと思ったのに、方向がどんどんずれていく。
おかしい、おかしいよ!
頭上で両手を合わせて頭を下げます!!
レイヴンじゃないですが、本当にすいませんでした・・。
他キャラの話し口調も把握しきれていないこの残念クオリティ。
これから先も、こんな感じでどこか明後日の方向に突っ走っていこうかと思います。
どうぞ生温い目でよろしくお願いいたします。
icon by Rose Fever
background & line by ヒバナ
