一
朝。
部屋に入り込む日差しを避けて横になったまま。
まだ目覚めるには早いだろうと、眠気にぼんやりとする頭。
特に用事があるわけでも無ければごろごろだらだらしていたい。
「ユーリ、ちょっと!」
「・・・へいへい」
そう思う傍から、階下から呼ぶ声がする。
女将の声に起床を催促され、仕方なしにあくびを一つ漏らしながらも階段を下りた。
「良い歳して朝からごろごろしてどうすんだ、ほら」
「ほらって・・まだ俺、朝飯も食ってねえんだけど」
手渡された買い物メモを見下ろして、あくびと共に出てきた涙を手の甲で拭えば、次に目を開けたときには目の前にこんがりと焼けたトーストが用意されていた。
本当に女将さんの手際はいいってこった。
椅子に座ってトーストにピーナッツバターを塗りたくりながら、ふと思い出した。
「そういや、あいつは?」
「ああ、だったらまだ寝てるんじゃないのかい」
当然のように返された言葉に、パンを口元に運ぼうとした手が止まった。
「・・何だよ。俺は叩き起こすのに、あいつは寝かせておくってか」
つい恨みがましい呟きがもれてしまった。
朝の仕込みで厨房で忙しく立ち回る女将さんの目が光る。
「あの子はこの前あんたが壊してくれた店の扉も、椅子も机も修理してくれたんだよ」
「・・・・・」
女将さんは本当に耳が良いなとか、扉が壊れた原因の半分は暴れた客なんだが、とかそういった思いが脳裏を過ぎったが、大人しくパンを食べることにした。
下手なことを言えば、次は飯も抜きになりそうだ。
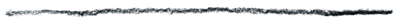
それでも、何となく理不尽な気持ちは抑えきれず。
カチャ。
無言で手をかけた隣の部屋の扉の取っ手。
手前に引けば何の抵抗も無く開かれたそれに、無用心だと思う気持ちと共に湧き上がるのは、どんな寝相をしてるか見てやろうという悪戯心。
「・・・・いねえ」
見透かされたように誰もいない部屋。
いつの間に起きて出て行ったんだと、空しい気分になる。
「・・・お、何してる?」
いきなりかけられた声に顔を向ければ、部屋の窓の上方から人の顔が覗いている。
ぎょっとして窓辺に駆け寄る。
「おまっ、そこで何してんだよ」
「・・・いや、だからそれはこっちのセリフ」
ひょいっと引っ込められた顔を追って、窓から顔を出して見上げれば屋根の上からきょとんとした瞳がこちらを見下ろしている。
フードの暗がりの中で、青緑色の瞳が不思議そうに瞬いている。
屋根の縁にあぐらをかいて顔を下方に向けている、その姿勢に落ちやしないかとひやひやさせられる。
「危ねえから、降りて来い」
「いや、もう何度か登ってるから大丈夫。慣れたよ」
平気平気とひょうひょうとした相手を、取り合えず無言で手招きすれば首を傾げつつも降りてきた。
掴んだ屋根の縁を軸にして体を回転させて、部屋の中に飛び込んでくる。
本当に身軽な奴だ。
「で、何か用だったのか?」
「ああ。お前暇だろ?買出し付き合え」
「いいよ」
何だそんなことかと二つ返事で頷かれて、今までの自分の行動がだいぶ子どもじみていたような気がして、思わず溜息をついた。
階段を降りてから気が付く。
「朝飯は?食ったのか?」
「朝は食べない」
「食べねえと、一日動けねえぞ」
「ユーリはおかんか?」
呆れたようなの目線に、うっせと返す。
「動けなくなったら、そこらで寝るから心配いらないよ」
「そっちのが心配だっての」
そこらってどこだよ。
でもうっかり、道端や石段の上で寝こけてるその姿が想像出来て顔を顰めた。
「あのな、下町は気のいい奴らばっかりって訳でもねえんだ」
「うん」
聞いてるのか聞いてないのか。
頷くその視線は、店先の花からその周りをひらひらと飛ぶ蝶に向けられている。
じー。
目で追いながら完全に立ち止まっているその襟首を掴む。
「聞いてねえな・・ったく。おら、さっさと行くぞ」
「あ、悪い。つい」
襟首を掴んだことで、フードが外れそうになったのか片手で押さえるの頭をぐっと押す。
目的の魚屋は目の前だった。
「・・・やっぱ、魚が好きなのか?」
「んー、いや肉も魚もどっちも好きだよ。そこは普通かな」
しげしげと店先に並べられた魚を覗き込む後頭部に問いかける。
「ただ、見たことない魚ばっかりで面白い。これは?焼く?生?」
「ん?坊やが調理するのかい?そうだな、それだったら塩焼きにするのがその魚の旨みが出て一番美味い!」
興味津々と言った様子で覗き込んでいたに向かって、魚屋の親父が嬉しそうに応える。
ふんふんと頷くそいつに、更にこっちは今の時期なら煮込んでとか、この魚は臭みが強いから薬味と一緒にした方が良いと魚お料理談義は続く。
坊やと呼ばれたことは気にしていないらしい。
まあ、俺も最初は勘違いしたくちだしな。
「おっさん、そのくらいにしといてくれねえか。も、さっさと買うもん買って帰るぞ」
「あ、悪い。つい」
待ちくたびれた女将に怒られちまうとメモをちらつかせれば、全く悪びれた様子もなくは振り向いた。
「お使い途中かそりゃ悪かった。じゃあこれは坊やにオマケだ。色々聞いてくれた御礼だよ」
「いや、むしろ色々聞いたのはこっちなんだけど・・」
メモに書かれた魚を入れたケースを渡されて受け取る横で、オマケと言われて細身の魚を何尾か入れた袋を差し出され、は不可解な顔で魚と相手の顔を交互に見ている。
「あり難く受けとっとけよ」
「こいつらも坊やに美味しく食べてもらいたいってな」
「・・・・・」
笑顔で差し出された袋を、複雑な顔で受け取る。
そして頭を下げた。
「美味しく頂く。ありがとう」
また来てくれよと手を振られて、魚屋を後にする。
何だかんだで嬉しいんだろう、は受け取った袋を大事そうに抱えて歩いている。
もし尻尾があったら、ご機嫌に振られていそうな足取りだ。
そしてひょいっとこっちの抱えている箱の中を覗き込んだ。
「大きいな」
「今夜の夕飯に並ぶんだろうな」
とはいえ、こんなでかい魚を一気に何尾も買う必要あったのか。
氷も詰められた箱はくそ重い。
「こっちと換えるか?」
腕の中の袋と見比べて、にやりと目を細めて聞かれる。
無言で箱を持ち上げての頭に肘を当てた。
ごつと実にいい音がして、肘からもじんわりと振動が伝わる。
は片手で袋を持ち直し、もう片方の手で肘を打ち込まれた頭を撫でている。
「・・・善意の申し出に暴力で返すことはないだろ」
「お言葉だけあり難く頂戴しとくぜ」
さっきのあの目は善意だったかと、涙目になるをじっとりと見下ろした。
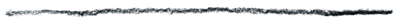
「んで、お前は屋根の上に登って何してたんだ」
女将さんに魚を無事に届けて、部屋に戻る。
涼しい風が開けた窓から入ってきて、窓辺に腰をかけるユーリの髪をさらさらと靡かせている。
窓辺に動かした椅子の背もたれに顎を乗せて、その動きを何とはなしに目で追う。
右へ左へ、ひらひらさらさら。
思わず、手で掴んでしまう。
「・・・人の話、聞いてねえだろ」
「あ、悪い。つい」
さらさらの手触りを楽しんでいれば、上から盛大な溜息が降ってきた。
その手が頭上に伸びてきて、避ける間もなくフードを払い落とされる。
「っ、おい、ユーリ」
「んー。何だ?」
意地が悪い顔、その指先に捕まれた耳。
さわさわ、さわりと 指先が耳の裏側をなで上げて、言いようの無い感覚が背筋をかける。
くすぐったいというより、もっと。
変な吐息が漏れてしまいそうなところを、目をぎゅっと瞑って何とか堪える。
「髪を勝手に触って悪かった。だから・・・離せ」
「俺の髪で良ければいつでも触ってくれて構わないぜ」
にやにや、するする、さわり。
「・・・やっ」
思わずびくりと首を竦めてしまう。
「猫も犬も、耳の後ろは弱いのな」
「・・ラピード!そう簡単に己の弱点を晒すな、今後気をつけてくれ!」
「ワフ」
知らんとでも言いたげに、足元に寝そべる青味がかった毛並みのユーリの相棒はそっぽを向いた。
まあ、長く相棒をしているらしいから、弱点というかそういうこともお互い知っているんだろうし仕方が無いのかもしれない。
何しろこの一匹と一人は意思疎通が出来る。
この男の持つ特技は確かユーリンガルと・・。
「何か、微妙に失礼なことを考えていないか、オジョーサン」
「気のせいだから、そろそろその手を離してくれ。あとオジョーサンって呼ぶな」
「オジョーサンはいじりがいがあるな」
この野郎。
笑ってられるのは今のうちだと思え。
「・・ユーリ、覚えておけよ」
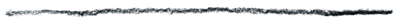
「いや、本当に昨日はすいませんでした」
目の前で殊勝に頭を下げる相手の髪の毛がさらりと揺れる。
それと同時に、飾られた装飾品がその頭上でシャラリと揺れて、澄んだ高い音を響かせる。
「お、どんな別嬪さんかと思えばユーリかよ!」
「ぶっはっはは、お前なんだその頭」
「お姉さん、こっちに給仕ー」
げらげらと笑う酒場に集う男に囲まれて、真っ赤な顔でユーリが拳を奮わせる。
「~~っ!!謝ってるだろ、これどうにかしろ!」
「?部屋で気付いたのなら、その場で取ればよかっただろ?」
夕方、寝こけているユーリの部屋にあっさり侵入。
その髪の毛を綺麗に編み上げて、頭上にまとめてこれでもかと飾り立てた。
夜のお仕事をしているお姉さんを参考に、だいぶ盛ってみた。
起きて気付いたら、自分で外して降りてくると思ったのに、寝ぼけたのか何なのか何故かユーリはそのまま降りてきて、そして今に至る。
「どうなってんのか良く分からねえんだよ!無理に引っ張ると痛えし」
確かに、そこここが微妙に乱れて差し込んだピンが数本ぶら下がっている。
それでもある程度の綺麗さを保っていられるのがすごい。
これはもはや芸術、か?
「良い仕事したな」
「おいこら」
「こんにちは。あれ、君見慣れない・・え?」
入り口の戸が開く音がして、謹厳実直が服を着て歩いているような青年が入ってきた。
爽やかな声が途中で止まる。
ついでに歩みも止まる。
ユーリはもはや俯いて、声も出ないようだ。
「フレン、おかえり」
「・・・、僕の目がおかしくなければそこにいるのはユーリに見えるんだけど・・あれ、僕の目がおかしいのかな」
「間違ってない。そこにいるのはユー・・」
言いかけた口元がガッと掴まれて、そのまま小脇に抱えられて宿に続く階段を駆け上がる。
すごいな腕力。
そのままユーリの部屋の扉が乱暴に足で蹴り開けられて、片腕でベッドの上に放り投げられる。
壁に当たりそうな上半身を捻って、受身を取って転がる。
危ないなと言おうとする前に、ベッドに乗り上げてきた相手で目の前に影が出来た。
目が、微妙に据わっていた。
「ここまでしてくれたんだ、覚悟は出来てんだろうな」
「いやまてまて、そもそもそっちが耳を勝手に」
撫で回してくれたんだろうが、と言おうとする前に伸びた両手がフードの合間から両耳をがしっと掴んでくる。
ひぃい。と血の気が下がった。
寝ぼけてそのまま降りてきたそっちが悪いんだろうという言い訳は、吸い込んだ息と共に喉の奥に消える。
その両腕を掴んで押し戻そうとするが、びくともしない。
これはだいぶまずそうだ。
蹴ろう、申し訳ないがそうしよう。
「・・・二人とも、何してるんだ」
「ひぃい」
開け放たれた扉の向こうに、にっこりと王子スマイルで笑うフレンが立っている。
良く来てくれたという思いを押しのけて、その背後に漂う黒っぽい、何かどろっとしたオーラに今度こそ悲鳴が口から漏れた。
何だ、これは敵か?
今の状況を見れば一瞬だけ救世主にも見えるが、どうしてもラスボスにしか見えない。
あれ?目が悪いのはフレンじゃなくて、自分?
「おいたをした相手にお仕置きだ」
「へえ、楽しそうだね」
二人とも普段は白と黒って感じなんだが、今はなんだ・・黒々としてる。
濃すぎです。
「そう、お楽しみ中なんだから邪魔すん・・」
「天誅!」
「ぐはっ」
つい、今だかつて叫んだことの無い単語を叫んでしまった。
余所見をしている間に膝を思い切り叩き込む。
腹を押さえてよろめいた隙に、飛び退って窓辺に駆け寄る。
「、窓は出入り口じゃないんだよ」
にっこりと笑うフレン。
その背後にこの部屋唯一の出入り口がある。
無理無理。
ゆらっと立ち上がった黒い魔王と、何だか知らないけど威圧感が半端無い白い魔王を倒して出入り口を目指せなんて、どんなチート使えばクリアできるんだっていう話だ。
「申し訳ない、魔王様。私の出入り口は窓なんで。ではこれにて失礼」
近寄る気配と伸ばされた手を掻い潜って、窓の縁から屋根の上へ。
まさかに追いかけてきそうな黒い魔王は、白い魔王に捕まったらしい。
その髪型似合ってるよ、ふざけんなてめえとかいう攻防が繰り広げられているらしい。
何はともあれ、二人が落ち着くまでは屋根の上にいるかと、横になって星を見上げる。
真っ暗な夜空に浮かぶ、結界魔導器の輪っかと星々。
その中でひときわ明るい星、凛々の明星。
アメストリスには無かったそれらを見上げて、目を閉じる。
夜行性の目に、それらはいやに眩しい。
それでも何だか眼裏に焼き付けておきたい気もした。
◆アトガキ
2013.9.27
はー。
長髪美人キャラに弱いです。
ユーリは性格もいいですしね。
他サイト様をうろうろさ迷った末に、ついに書いてしまいました。
でもまだ公式キャラはおろか主人公のことさえ掴みきれていない、ふわふわ感が否めません。
もっと把握して動かしやすくしないと、何か浮かんだときに上手く書けない・・。
もしかしたら、この先気が付いたら口調が変わっていたりするやもしれません。
先に謝っておきたいと思います、ごめんなさい!
icon by Rose Fever
background & line by ヒバナ
