一
「あ、セーネンごめん」
背後から聞こえた声に反応するより早く、視界を何かが掠めて落ちた。
「って、ぅおい!どんだけ失敗してんだよ!!」
「だから、悪かったって言ってるじゃない。あ、この際だから全体的に揃えて短くしちゃう?」
「や・め・ろ・・」
足元に落ちた長い黒髪に、項垂れたユーリから低い声が返ってきてレイヴンは意味もなく左手に持ったハサミをシャキンシャキンと動かした。
マンタイクで怪我を負ったユーリから、少しだけと頼まれた簡易床屋は早速仕事を失くしてしまったらしい。
どうしてユーリが長い髪に拘るのかは分からないが、短髪も似合いそうなのにとレイヴンは椅子に座る後頭部を見る。
「・・・・・」
すっきりさっぱりさせた姿を思い浮かべる。
その傍にパーティメンバー(の女性陣)が集まっている様も容易に想像できて、レイヴンは無言でハサミをしまった。
今なら、今のままならまだユーリの髪の長さに救われているということに気が付いた。
もし青年が「青年」らしい髪型をしてしまったら・・・。
「そんなのは認めない。俺様は認めないーーーー!!」
「何だよ、唐突に。てか、うるさいぞ」
はぁあと溜息を吐いたユーリが、椅子から立ち上がってすっと左手を伸ばしてくる。
頭を抱えたポーズのまま、レイヴンは無言でその左手を見つめ返した。
「ん」
「・・何、その手」
「何って・・ハサミ」
ああ、と頷いてレイヴンは片手に持ったままのハサミをその手に返した。
「・・本当に悪かったと思ってるわよ」
「ほんと、一房で済んで良かったぜ」
次はジュディにでも頼んだ方が良いかもな、と零すユーリの言葉にレイヴンは目を剥いてその両肩に手を置いた。
ガシッと掴まれた方も驚いたように目を丸くするが、そんなことにはお構いなしにレイヴンは吠えた。
「短髪は似合わないからね!駄目だからね、セーネンっ!!」
至近距離の勢いに少し引き気味になったユーリはそれを聞いて、半眼になった。
「・・言われなくても、やんねーよ」
やれやれと肩を回しながら部屋を出ていくユーリの後ろ姿に、レイヴンは見えないように小さくぐっとガッツポーズをした。
良かった・・!!
短髪のせーねんにジュディスちゃんやちゃん、エステル嬢ちゃんやリタっちが絡んでる姿なんて、おっさん見たくない!!
密かに青年ハーレム妄想に涙しそうになったレイヴンの心の叫びが、静かな部屋の中にこだました。
トントン
「はーい・・?」
「レイヴン、開けていい?」
扉の向こうから聞こえたの声にレイヴンは椅子を片付けながら、いーわよ、と答えた。
すっと開けて中を見渡したその目に、床に落ちていたそれが映る。
「ん、あれ・・これって」
「あー・・青年の髪、ちょっち切りすぎちゃって」
「ああ、やっぱり・・」
ユーリのかと呟いて、はひょいとそれを拾い上げた。
「ところで、ユーリは?」
「あら?さっきハサミを持って出て行ったはずなんだけど・・会わなかった?」
こくりと頷いてしばし思案したように顎に手を当てて俯くその姿に、何かあったのかと不安になったレイヴンが声をかける前に、すっと上げられた顔がこちらを向く。
「ハサミ、ユーリが持ってった?」
「あ、ええそーね」
「分かった、ありがとう」
何故か手に切られたユーリの髪を持ったまま、は入ってきたときと同じように何でも無さそうな顔で部屋を出て行った。
そんなを見送りながら、後ろ頭に手をかけてレイヴンもしばし考え込んだ。
切ったユーリの髪をどうするつもりなのか。
まさか・・・呪い、とか?
いやー・・・。
「いくらなんでも、それは無いわよねー」
そんな非科学的なこと!と、リタが聞いたら怒りそうなものだ。
ははは、とレイヴンは自分の想像を笑いで何とか打ち消した。
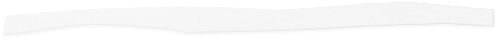
静かな夜の部屋。
眠りに着こうと枕に頭を預けた。
ふわっ・・パチッ
「!?・・なんだ・・・?」
後頭部辺りで何か静電気のようなものが起こって、ユーリは横になろうとした体を慌てて起き上がらせた。
振り返って枕をしばし凝視する、も何もない。
左手でぽんぽんと軽く叩いてみるも、やはり何もない。
「・・気のせいか・?」
静電気、だったのかもしれないと思いつつも、一度湧き上がった警戒心はなかなか消えてくれなくて、枕をひょいとその場から退かす。
久々の宿での就寝ではあるが、元々寝ようと思えばどういう場所でも寝られるしと、平らなシーツの上に横たわった。
自らの腕を枕に、旅の疲れに背中を押されるようにユーリは眠りに落ちた。
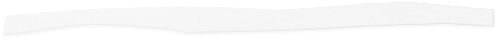
「せーねん・・それ」
「ん・・・?」
朝、寝ぼけ眼を擦って起き上がれば、先に目を覚まして動き出していたらしいレイヴンがこちらを凝視して固まっている。
何事だろうと、ぼけっとした頭で見返すも、心辺りがあるわけもなくユーリは開けきらない瞼のまま首を小さく傾げた。
「何だよ、おっさん・・」
「何だよって・・・え?」
「?」
昨日、自分が切りすぎてしまった髪の毛が、何事も無かったかのように伸びている。
もはや元通りとも言えるその長さに、レイヴンは穴が開きそうなくらいにユーリの毛先を凝視した。
人間ってこんなに早く髪の毛伸びるもんかしら。
そういえば、エロい人は毛の伸びも違うとか聞いたことあるし、何しろユーリだ。
普段から露出し過ぎやしないか、女子供らの前でよくもそう堂々と胸元肌蹴てられるなー、とか思っていたし。
もしかしたら、髪の毛もそんな早く伸びるものなのかもしれない・・・。
「おい、聞こえてんぞおっさん。朝から人のことエロいとかどういう了見だコラ」
でもそれなら今頃ユーリの髪はとっくに地についている、と腕を組んで悶々と考えていれば、それらはぶつぶつと声に漏れていたらしい。
ベッドに浅く腰掛けた相手に、半眼どころか殺気を漂わせたような目で睨まれる。
「いやいや、セーネンの露出狂に関してはまた置いておいて」
「いや、俺としてはそこんところ、この際だからきっちり話つけといた方が良さそうだなと思うんだが・・・なぁ?」
「ちょ、って何で武器なんて持ってるのよ?!だからいやそうじゃなくて、今は違うのよ!」
「・・ほんと、朝っぱらからなんだよ」
「髪!髪の毛だってば!!!」
「・・・・は?」
どうどうと掌をしたに向けて抑えてとジェスチャーすれば、ユーリはしぶしぶといった様子でやっと持っていた武器から手を放した。
寝起きのせいでいつもより少し据わった目が、溜息を共に瞼の裏に隠れた間に、レイヴンは胸元に手を当てて小さくほっと息をつく。
再度目を開けたユーリは、怪訝な様子で自身の髪をまとめて前に持ち上げて見始めた。
「・・・髪が、なんだよ」
「だから、髪の長さよ!」
「言いてーことが良く分かんねぇんだが・・いつも通りじゃねーか」
言って、首を傾げる相手に、レイヴンは上手く伝えられないことにもどかしくなってあああっと頭を抱えそうになった。
「だから、いつも通りなのがおかしいんだってばセーネン!・・昨日、俺様が間違って切りすぎちゃったじゃないの!!」
言えば、ようやく合点がいったのか、目の前に髪の先を掲げたままユーリの動きが静止した。
極限まで見開かれた目がまじまじと自分の髪を見ている様に、やっと伝わったとレイヴンはほっとしかけて、いやいや違うだろうと首を振った。
「おかしいでしょ!」
「いや、あ・・えーとそうだな・・おかしい」
上手く脳が働いていないらしい。
自身に起きた出来事に信じられないといった顔で、何とかそう答えたユーリの顔が不意にハッと上げられた。
ブーツを履くのももどかしいといったように、バタバタと動き回って帯もせずに羽織っただけの上着のまま部屋を出て行こうとする。
「ちょっと、ユーリどこに・・」
「説明は後、なっ」
言って慌ただしくユーリは部屋を出て行ってしまった。
そうなったことに何か心当たりがあるようだった。
しばし考えて、レイヴンはにやりと笑う。
ついていかない、わけが無い。
こんな謎な現象にちゃんとした理由があるなら、知りたくなるってものでしょ。
抜き足差し足、ぐっすり眠っているカロルを置いて、レイヴンは気配を殺してそっと部屋を出た。
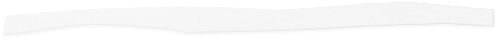
「っ・・どこ行ったんだよ、あいつ」
ごつごつとブーツの鳴る音が宿屋の木製の廊下に響く。
先ほど、早朝から悪いと思いながらも女子部屋に当てた部屋の扉をノックすれば、こちらもとっくに起きていたらしいジュディスがにこりと微笑みながらどうぞ、と扉を開けてくれた。
だが、ちらと見渡した中にあいつの姿だけが無い。
「ジュディ・・は?」
「あら、が目的?」
「そーいうんじゃ無えっての・・・で」
「なら、私が寝る前にはもう居なかったわ」
戻ってきてもいないわよと続いた言葉に、早朝から悪かったなと出て行こうとすればジュディスはくすくすと笑った。
「何だよ・・」
「夜這いがしたいのなら、鐘楼の上がオススメよ」
前半部分に何かを言い返そうとした言葉が、喉の奥で消える。
「おはよう、ユーリ・・行ってらっしゃい」
肩掛けを羽織って胸の下で緩やかに腕を組んで静かに微笑む相手を見て、ユーリは肩を落とした。
ジュディスの言葉に、挨拶すらしそびれていた自分に何をそんなに焦っているんだと、溜息を吐く。
「ああ、おはようジュディ・・サンキュ、行ってくるわ」
「ええ。によろしくね」
優雅に手を振るクリティア族の女性に、小さく笑って手を振り返しユーリは宿屋の外に足を進めた。
「・・おじさま」
「!あ、ええっとおはようジュディスちゃん」
廊下の壁の裏に立つレイヴンの肩がびくっと跳ね上がる。
そちらを振り向きもせずに声をかけたジュディスに、しぶしぶとレイヴンは姿を現した。
「もー、バレちゃってたのね」
「駄目よ、おじさま」
「でもジュディスちゃん、これは二人の仲をどうこうとかじゃないのよ!ミステリーなの!!」
ジュディスの赤ワインのような瞳が少しだけ見開かれたのを見て、レイヴンは辺りをはばかるように口元に手を当てながら、昨日から起こったおかしな出来事を話し始めた。
「そういえばちゃん、昨日床に落ちてたセーネンの髪の毛を拾って部屋を出て行ってたわ・・・」
「・・・そう」
同じように不思議そうに首を傾げて考え込むジュディスに、レイヴンはそわそわとした気分を隠すことができない。
あー、今すぐ追いかけたい、でも朝からのジュディスちゃんのこのナイスバディも、もうちょっとだけ拝みたい・・!
「・・おじさま」
「はっ、はぃい?」
思わず口に出していたのかと口元に手を当てれば、ジュディスは妖艶に微笑んでそっと腕に手をかけてくる。
レイヴンは素直にドキッとした。
「私たちも、行ってみない・・?」
「えっ!」
良いの、ジュディスちゃん?!と瞠目すれば、にっこりと意味深な笑みを浮かべてジュディスは頷く。
「私もその謎、気になるわ」
力強い味方を得たレイヴンも、意味深な笑みを返す。
「それじゃあ、ジュディスちゃん早朝デートと行きますか」
お手をどうぞ、と左手を差し出した。
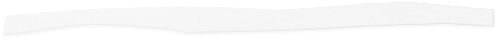
「・・・・ったく」
何でこんなところにいんだよ、と白み始めた空に半身を照らされている相手を見下ろして深々と溜息を吐いた。
ジュディスに教えられて、町の一番高い塔を上り鐘が吊り下げられた場所へたどり着けば、低い天井の下、ユーリの腰よりも低い石造りの壁にもたれかかるようにしては寝ていた。
大方、夜通しこっから眼下の景色を眺めていたんだろうけど。
「落ちたら、骨折じゃすまねーぞ」
狭い鐘楼は、本当に鐘を鳴らすためだけの場所らしい。
鍵はかかっていなかった塔の中の梯子をずっと上ってきて、扉というか蓋というか四角い板を押し上げれば、体を外に出さずともそこから鳴らすための紐にすぐ届く。
梯子から上半身を出せば低い縁に寄り掛かるに、さすがのユーリも肝が冷えた。
真っ直ぐに立つことが出来ないので、鐘の脇にしゃがみ込む。
「・・・・・」
どこかで早起きの鳥の鳴く声に、無意識にだろうの耳がピクリと揺れた。
だが、すうすうと寝息が聞こえるあたり、まだまだ眠りの底にいるらしい。
手を伸ばしてその髪を撫でる。
「・・・」
返事の無い眠っている相手をそっと引き寄せる。
あぐらをかいてその上に抱き寄せた体は小柄で、早朝の風に少しひんやりとしていた。
自分の熱が伝わるように、それ以上冷えないようにと腕で囲って縁にもたれかかる。
「・・なあ、お前が探してるお前自身ってのは、今のお前じゃ駄目なのかよ」
応えは、無い。
朝の金色の光が、地平から徐々に空を染めていく。
追いやられるように消えていく薄暗い青色を眺めながら、いつかが言っていたことを思い出していた。
この体は、作られた継ぎはぎの紛い物なんだ、と。
自分のものでは、無いのだ、と。
「でも、俺は・・俺が出会った今ののこと、割と気に入ってるんだけどな」
見下ろした視界に、自分の髪が流れ落ちての顔に影がかかる。
払いのけようと摘まんだ自身の髪に視線を落とした。
そんな、人の体をツギハギなんて出来るわけが無いと、最初は話を聞いても信じられなかった。
でも、こういうことが出来るやつなんだ、コイツは。
こういうことが出来る世界から来たんだ。
今でも信じられない気持ちはあるけれど、分かってはいるつもりだ。
だからこそ。
理解した今だからこそ。
「今のままのが・・結構好きなんだけど、な」
呟けば、眼下の相手がもぞりと身動きした。
んーと小さく唸って、もぞもぞと擦り寄ってくる。
「やっぱ寒かったんじゃねーのか?・・・おい、起きろよ」
「う、んんー・・・?」
「、宿に戻るぞ」
「ん、あれ?」
眠たげな瞳がゆっくりと開閉する。
まだ、起きているとは言い難いぼおっとした顔が、きょろりきょろりと辺りを見回して、自分がどこにいるのかを確認しようとしているのが分かる。
「・・・ここは・・」
小さく呟きかけた言葉は、あまり聞きたくなくても静かな朝の空気の中、耳に届いてしまった。
アメストリス、じゃない。
そう、聞こえた。
「ん、そか・・のぼってきたんだった・・ユー・・リ?」
見上げてきた青緑色の瞳が、まだ薄ぼんやりとしていて、それでも名前を呼んできたことに内心ほっとする。
「何故、ここに?」
「迎えにきてやったんだろ」
そう返せば、いつもはあまり表情が出ない顔が、へにゃりと笑った。
まだ寝ぼけてるんだろう、そう呆れて見下ろした耳に届くふわふわとした声。
「ありがとう、ユーリ」
思わず、瞠目してしまった。
もぞもぞと起き上がったは、そんなこちらの様子には気が付かず縁から少し身を乗り出して外の景色を見始める。
「ああ、どこにいても、明け方って綺麗だな」
見入ったように、端から広がる金色の光とそれに染まっていく森や町並みを眺めるその横顔が輝いている。
和むように細まった瞳。
どこにいても、の意味が分かる俺は、それを咀嚼して飲み干した。
「・・・ああ」
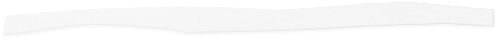
「そういや、どうしてわざわざここまで?」
「お前・・枕に何か仕掛けたろ」
梯子を下りながら、塔内に反響するので声を落として会話する。
「あー・・ごめん、もしかしてそれで寝られなかったのか」
「いや、眠りはしたんだが。・・レイヴンが」
言いかけたユーリの声が途切れる。
先に梯子を下りていたは、上を振り仰いだ。
はずみで落ちそうになったフードを手で押さえれば上から見下ろす視線を感じて、片手でそれを抑えながらユーリの顔を見上げた。
「ユーリ?」
「・・そろそろ、みんなに話してもいいんじゃねえか」
何を?、と返すほどにはもう眠気は無くて、は開きかけた口を閉じてまた梯子を降り始めた。
真っ直ぐな塔の内部は、上方の壁に明り取りの小窓がいくつか開けられているだけで薄暗い。
降りていけば明るさに慣れた目にはまだ暗い空間が広がっていて、その闇の中に歩を進めていくことに少し躊躇いがちになった。
「・・」
「分かってる。きっと皆、受け入れてくれるってことは」
結局立ち止まってしまったこちらを気遣うように、ユーリが名前を呼んでくる。
その優しさに、上手く答えられない自分がもどかしい。
分かっている、分かってはいるのだ。
こうして旅をしてきた仲間が、みんな良いやつだってことは。
誰に打ち明けても、驚かれる顔は想像出来ても嫌悪や、ましてやどうこうしてやろうなんていう顔は誰一人として思い浮かばない。
それでも躊躇してしまうのは。
「どこまで・・・」
別の世界から来たってこと。
錬金術については、戦闘上使わないわけにもいかず、それとなく話してはいる。
それから、この耳のこと、体のこと。
「少しずつで、良いんじゃねーか」
よっと、と残りの数段をジャンプしたユーリが、先に地面に足をつけて見上げてくる。
ほら、と差し伸べてくる手と腕を困惑しながら見れば、苦笑したユーリの手がすっと伸びてきた。
「!っ・・ユーリっ?!」
避ける間もなく腰元に絡められた腕に、梯子から引きはがされる。
慌てた声も取り合わず、笑うユーリにそのまま担ぎ上げられた。
下してくれと抗議するも、無視される。
「薄々気づいてるんだろ」
「・・・ユーリ」
「周りの奴らが、が言い出すの待ってるってこと」
迷子のようなの声を肩口で聞きながら、ユーリは歩き出す。
「それにな」
「・・・ん・・」
「悪ぃ、もう聞かれちまったみたいだ」
「・・・・へ?」
悪戯そうに笑うユーリが開いた塔の扉の向こう、気まり悪げに後ろ頭をかくレイヴンといつも通りに笑うジュディスが並んで立っている。
「おっさん、上から丸見え」
「えーっと・・ごめんなさいね、ちゃん」
おっさん聞いちゃった、という告白に目が真ん丸になる。
すっと近づいてきたジュディスに思わず下がろうとした体は、ユーリに担ぎ上げられていることによって叶わず、いつもと違って同じ高さにある視線に居心地悪く身じろぎをする。
「・・ジュディス・・」
緩やかにそのワインレッドの瞳が細められて、戦闘によって少し固い手のひらが伸びてきて思わず目を瞑った。
細い指先がそっとフードの中に潜り込んできて、迷わずにたどりついた耳の先を撫でる。
「ふふ、ごめんなさいね。でも私、好きよ」
あなたのこの耳、と顔を寄せて囁かれるのにびくりと体を震わせてしまった。
「ジュディ・・・くすぐったいんだが」
「あら、ユーリに言ったんじゃないわよ」
「・・・分かってるよ」
息を吐いたユーリによって、やっと地面に下される。
おずおずと見上げた先にジュディスとレイヴンの笑顔を見て、開きかけた口を一度閉ざして、また開いた。
「・・・言えなくて、その・・・待たせて悪い」
「いいのよ」
「良いってこと」
レイヴンの手によしよしと頭を撫でられて、つい強張っていた頬が緩む。
「そうと決まったら、あいつらにも言ってやらねえとな」
きっと、うるせえぞと意地悪気に笑うユーリが、さりげなく頭上のレイヴンの手を叩いているのに、また小さく笑う。
リタはともかく、残りの二人は何も気づいていないだろうと腕を組んで言うユーリの言葉に、ジュディスが頷いて同意する。
「朝っぱらから騒がしくすんのも悪いしな」
「まずは朝ご飯、ね」
おっさん、お腹ぺこぺことお腹を押さえて歩き出すレイヴンの後に続く。
朝ご飯をみんなで食べて、町の中が動き出したら少し賑やかにしても許されるだろう。
さて、どこからどうやって話そうかと考えていることに、は自分でも驚いていた。
二人があまりにも自然に受け入れてくれたから、一気に抵抗感が無くなってしまった。
カロルやエステルに話すのだと思えば少しでも深刻にならないように。
アメストリスでのこと、例えばあの兄弟の面白い話とかも織り交ぜて、笑顔で伝えられたらいい。
それから、謝るのだ。
「なかなか言えなくてごめん。・・・ありがとう」
そっと口にした言葉は、ちゃんと聞こえたらしい。
伸びてきた手に肩を叩かれて、頭を撫でられて、くすぐったい。
胸の中が、暖かくなった。
ちょっとだけ・・泣きそうになった。
◆アトガキ
2014.6.2
Do you see what I mean?
「ほら、な?」
ずっとパーティーメンバーに隠していたので、いつかは言わないととずっと思っていた、耳とかの話です。
エステルとカロルはもう純粋に驚いて、かつエステルには存分に撫でまわされそう。
リタは一見興味ないふりをしながら、すごく興味津々です。
周りにつつかれて真っ赤になってそっぽ向くけど、好奇心抑えられない感じ、可愛いよリタ。
二人きりになった時に、存分に触らせてあげてついでに錬金術の話とか研究の話とか盛り上がって、結局二人で徹夜の流れです。
icon by Rose Fever
background & line by ヒバナ
