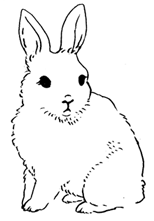「肌寒いな」
夕方になって暗くなった空を見てからカーテンをシャット閉めて長い黒髪を揺らした長身が振り返る。
春になって温かい日差しがやっとお出ましかと思いきや、まだまだ日が差さなくなった時分は肌寒い。
カーテンを隙間なく閉めたのを見てから足元のホットカーペットの電源をオンにした。
これだけでは部屋中が温まるには力不足だが床のそのまた下から昇ってくる冷気をシャットダウンしてくれるくらいには頑張ってくれるし、足先が冷える自分には無いとあるとでは大違いだ。
少しでも温かさを留めるために、また余計な冷気を入れないためにカーテンを閉めたら小さなヒーターにもスイッチを入れた。
「お湯沸かすね。何か飲む?」
「甘いもん」
ヒーターの前にどっかりとあぐらをかいたユーリがこちらを振り仰いで注文するのは、まあ予想出来ていた。
ココアか、ミルクティーか、ゆず蜂蜜か、と取りあえずやかんに水を注ぎながら考える。
「あ、あれがいい」
「アレ?」
あれって、どれだ。
そんな熟年夫婦のようなツーカーな仲では無いから、甘いもの、のその先が何かまでは分からない。
んー、っと、とのそのそと立ち上がった相手は、開けた冷蔵庫の中をごそごそと見漁って見つけた何かを取り出して見せた。
今やこの冷蔵庫の中のものはユーリが半分以上管理しているような状態である。
ちなみにユーリの最近の趣味は近所のスーパーのチラシを見てより安く質の良い食材をゲットすることで、順調に主夫への道を歩んでいる。
但しうさぎ姿で無い時、限定。
「あんこ・・」
「まだ残ってたよな、ん、あったあった」
棚の中から個包装の切り餅を出したユーリはそれを適当なお椀に入れ、その上にあんこを適量のせてよこした。
「好きだね、お汁粉」
「甘いしお腹も満たされるしな」
まだ出来てもいないのに食べた時のことを思い出してか目がキラキラしている。
「あんたの分も・・」
作ろうかと促され、やかんのお湯が沸くのを待ちつつ自分も食べようかどうしようか迷い、そして唐突にハッとした。
「いや、いいよ。私はお茶にしておく」
慌てて手を振ってそれを断った。
いかんいかん。
最近ユーリにつられて甘いものを食べ過ぎていることを思い出した。
美味しそうに食べる相手のその至福そうな顔を見ていれば、気付いた相手から「お前も食べるだろ?」と一口寄越されるのもしばしばで。
最初こそ自分はいらないと自制しつつも、一口だけならとついつい頂いてしまう日々が続いてしまっていた。
そうなると無視できないのが自身の体型だ。
最近お腹の周りがふっくらぽったりしてきてしまっている。
これ以上はマズイ。
寄越されたお椀にお湯を少量注いでレンジにかける傍ら、自分の分は砂糖無しの紅茶を淹れる。
傍に立ってお汁粉が出来上がるのを待っているユーリのその細腰をチラと見て、そっと視線を逸らした。
「ん?どうした?」
「いや・・何でも」
ふっと吐いた溜息に気付いてこちらを見て声をかけてくるユーリに何でもないと手と顔を振る。
半分人外といってもいい、間違いなく自分と違う種族だと思いつつもその適度に筋肉の付いたすらっとした体形を横にして自分の体型が気にならないわけが無い。
全体的に細いくせに無駄に力があるなんていう事実を知ったのは不可抗力だ。
寒い寒いといって気が付いたらベッドに潜り込んでくるヤツと同衾をかましてしまったのは、もう一度や二度では無い。
態のいい抱き枕、いや湯たんぽとして見られているのではなかろうか・・・。
「うさぎのくせに」
「・・、何だよいきなり」
諸々のことを思い出して睨みつければビックリしたような顔でたじろぐ。
その一瞬後に、自分は何も悪いことしてねえぞと言いたげにムッと寄せられた眉をじろっと見上げた。
「言いたいことあんなら、」
言いかけたユーリを遮るように出来上がりを知らせたレンジを無言で開けて中身をズイッと差し出す。
無言で受け取ったユーリは、まだ何か言いたげにしながらも引き出しから箸を取り出してテーブルについた。
「・・・・・」
紅茶の葉をポットに入れてお湯を注いで、踊る葉っぱを見てまたそっと溜息を吐いた。
分かっている。
ハッキリと言わない自分も悪い。
本当に嫌ならもっと本気で拒絶するべきだ。
でも、と。
テレビをつけてそれを横目で見ながらはふはふとお汁粉を食べている黒うさぎを見た。
「・・?」
勘が良いユーリが振り返って微かに首を傾げる。
目を瞑って首を振る。
ユーリが少し眉根を潜めたのが視界の隅で見えた。
「・・、なぁ」
夕飯も食べて夜も更けてお風呂にも入った。
のんびりと過ごして後は良い時間になったら寝るだけだ。
ぼんやりとテレビのバラエティー番組を見ていた耳に、そっと低い声が届く。
考え事をしていた、その相手からかけられた声に瞬きをしてそちらに視線を向ければ、頬杖をついているその視線はさっきまでの自分と同じようにテレビの方を向いていて、さっき聞こえた声は空耳だったのかとまたテレビの方を向こうとした。
その視線がふっとこちらを向く。
「」
呼ばれて、さっきかけられた声が幻聴では無かったのだと分かる。
何だ、という意味を込めてその目を見返して続きを促す。
「オレ、さ」
その言葉の先が何となく分かってしまった。
ユーリがここに来てから少したって、その存在が気が付けば馴染んでいて・・その頃からお互いふとした瞬間に真顔で押し黙ることが増えてきた。
その言葉の続きを、何でもない顔で笑い返すことで避けてきたのは自分だ。
どうしたいのだろう。
このままでもいいのか。
どこかぬるま湯のような心地よい空間に、このまま浸っていたい気もして。
「ねえ、ユーリ」
でも、そうじゃない。
このままズルズルとしていたってお互い喉の奥に引っかかった小骨は取れない。
だから。
「・・オレ、ここに」
「貴方に首輪をつけさせて、ユーリ」
「っ!!」
「嫌なら、出て行って」
見開かれた夜空のような濃い紫の瞳をじっと見つめる。
その口元が僅かに開かれて、そのまま何か言葉を探すように口ごもりそして俯く。
長く綺麗な黒髪がさらりと顔の前に流れ落ちればその表情は暗がりに隠れて全く見えなくなった。
自分の言葉を反芻して、その酷さに自嘲する。
付き合って、と言ったわけでは無い。
なのにその存在を勝手に縛らせて欲しいと、まさにペットに首輪をつける様に自分勝手な気持ちを押し付けた。
さすがに呆れているだろう。
私が偶然に拾っただけ。
きっと彼なら他のどこでも自由に生きられる。
・・うさぎだったり、人間だったりする謎な生物だけど。
「分かった」
俯いたまま、低い声がハッキリと答えた。
その言葉を最後通牒のような気持ちで受け取る。
これで、このおかしな関係はオシマイ。
きっと一人で寂しいなんて思っていた自分へ、神様が気まぐれにくれたプレゼントだったのだ。
夢のような、・・意地悪で温かい時間。
でもどこか胸のつかえが取れたような気がしていた。
終わりを予感しながら、いつ宣告されるかと心のどこかで怯えながら暮らしていた日々が終わる。
「じゃあ、」
言って立ち上がるユーリの気配を、目を瞑ったまま感じる。
動いて、そしてきっと立ち去る。
自分の傍で風がふわりと揺れた。
「あんたの首にも、付けさせて」
座る自分の背後で立ち止まったユーリの低い声が落ちてくると同時に、首の回りに緩やかに何かが巻き付く。
開いた視界の端にユーリの服の袖と、視界を遮るように上から落ちてくるサラリとした長い黒髪が首筋を滑っていく。
「・・・ダメ?」
ズルい。
ゆっくりと絡まる腕に頭を傾ける。
温かい。
もう自分はこのぬるま湯から抜け出すことなんて、到底出来ないんだと分かった。
腕の中に大人しく収まっている存在にほっとする。
巻き付けた腕に頬を寄せて微かに振られた後頭部に心の底から広がる気持ち。
温かい。
絶対に離れたくないし、誰にもやりたくない。
本当いえばこんな相手の生活に寄生しているような状況は抜け出したいと思わなくもないけど、こんな中途半端な存在誰も好んで引き取ってくれる奴はいねえだろうと思っていた。
寂しさに付けこんだのはよく分かってる。
だから、最初に謝った。
眠たそうな顔したにはちゃんと聞こえてないって分かってたけど。
抱きしめた腕に力を込める。
これであんたは俺のもの。
抱き寄せて膝の上に乗せたはまだ何となく今の状況を飲み込めていないようなふわふわした顔をしている。
後ろから手を回してお腹の辺りをぐっと引き寄せれば、何故か急に暴れ出した。
何だ?
「待った、ユーリ放して」
「ヤダ」
「は?!」
しれっとした顔で却下すれば眉が跳ねあがる。
身の危険でも感じたようにジタバタともがく身体を抑え付けて項に鼻先を埋める。
「っ、くすぐったい」
抗議の声を無視して鼻先で柔らかい髪を掻き分けて覗く項にキスを落とす。
ちゅっと鳴った音にびくっと小さな肩が震えた。
カワイイ。
思わず後頭部に頬を摺り寄せて、ふぅと息を吐いた。
危うく本当にがっつきそうになる。
実を言えば何度もうさぎの習性にかられて押し倒したくなる気持ちをずっと我慢していた。
すやすやと寝るを起こしてかき抱いて思うがままに貪りたい衝動も何とか我慢していた。
だって、なあ・・ただ拾っただけ、面倒見てるだけの相手(しかも半分獣)に食われそうになったと分かったら、さすがのこいつも警戒して追い出すくらいすんだろ。
だから、その関係を変えなきゃいけねえとは思ってた。
でも働けねえ(うさぎだから)タダ飯ぐらいの奴が調子よく言い出せることじゃそうそう無くて。
「ん、もうユーリ!もう寝るから」
「んー・・そうだなー」
柔らかくてあったかい存在を自分が望むようにして良いなんて、どんな幸せだろう。
勢いでがっついて早々に嫌われて追い出されるのだけは何とか阻止したい。
少しずつ、ちょっとずつ慣らしていかなきゃな。
・・添い寝はもう許してもらってるようなもんだけど。
「?!ちょ」
ぎゅっと抱きしめたまま、ラグの上にごろんと転がる。
押し潰してしまわぬように、でも腕の中から逃げ出されない様に自分の体と腕の間に閉じ込めてみた。
肌蹴た部屋着の裾から脚を絡めて動けない様に足元を固定すれば、もがいていたは疲れたのか溜息と共に身体の力を抜いた。
・・・、少しずつ、少しずつ。
自身に言い含める様にしながらも巻き付けた片腕が勝手に動く。
すす、と下していく先は割った足の間。
「ユ、ユーリ・・っ」
「ん」
焦ったように呼ばれた声に頭がぼぉっとする。
受け入れられた状況に気を良くして、いつもは働く理性が霞がかったように脳の片隅に追いやられていく。
縮こまる様に足を曲げれば覗く膝を上へと撫で上げれば、は息を飲むようにして体を強張らせた。
ぎゅっと固まる身体はそれでも十分触り心地が良くて、その柔らかさをもっと感じたくて服の内側へ、大腿に手を這わせる。
挟んだオレの脚が邪魔で閉じきれない太股はさらさらと触り心地が良くやわやわと揉みしだいていれば、次第にしっとりと汗ばんでくる。
不快感とは無縁のその手に吸い付くような感触に夢中になれば、腕の中のが微かに震えているのに気が付いた。
「!・・?」
ヤバい、泣かせたかと慌てて名前を呼べば大げさなくらいにその肩が跳ねた。
「・・・・・」
そのままシーンとした沈黙が落ちる。
もしかして。
何も言わないの様子を窺いながらそっとまた手を内股に這わせれば、喉の奥に押し込めるような小さな声が漏れ聞こえた。
耳に届いたその声とヒクリと小さく震える身体の熱が一気に上昇する。
「、」
耳元で確かめる様に名前を呼ぶ。
もしかしてコレは泣いてるとかそういうんじゃなくて、もしかしたらもっと・・。
「ま、待って」
その耳が赤みを帯びていて色々振りきれそうになる前にの声が聞こえて、やっとの思いで手の動きを止める。
お互いドキドキしているのがひっついたままの体から伝わってきて、部屋の中はもう大分前から寒さを感じない程ではあったけれど。
落ちた沈黙の中に鼓動の音さえ聞こえそうで、そっと息を詰める。
「・・ま、まだちょっと・・・こわい」
詰まらせた吐息の間から、小さく零された声にぎゅっと目を瞑って大きく息を吸った。
「ご、ごめん・・」
ユーリ、と名前を呼ばれて吸ったまま止めていた息を吐きだすように、あー・・と脳内で行き場の無い気持ちを押し殺していく。
そうしてから、長く長く息を吐いた。
「いや・・、オレが悪かった」
「でも」
「いい」
いいから、と足元から放した手でその体をぎゅうっと抱きしめた。
息苦しそうにうっと詰まった声を出すに悪いと思いつつ、しばらくそうしていた。
◆◇*------------*◇◆
illust by Blancma
background by *ヒバナ * *