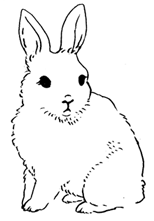「・・、そこでいったい何をしているんです」
背後からかけられた声にギクリと肩が跳ねる。
いつの間に入ってきたのだろう。
扉が開く音も足音すら気が付かなかった。
こんなに静かな空間だったのに。
・・・、いやわざと気配を消してきたに違いない。
「何って・・・読書、とか」
動揺しながらも何とか答えてみたが、近づいてからわざと立てる音は自分のすぐ傍でカツリと立ち止まった。
「・・、確かに君が読書を趣味としていることは知っている」
でも、と続く低く平坦な声と共に手に持っていたその分厚い資料は、黒い手袋に包まれた指先が掴んで手の中から引き抜いていった。
「これは全く持って読書向きでは無いよね」
「・・・・・」
ちらと見下ろしてくるモノクル越しの赤い瞳が、冗談を言ってかわせるような状況を許してはくれなかった。
確かに全く持って読書向きではないし、むしろ見ていて目は疲れるし正直ちょっぴり眠たかった。
「私は君に部屋に戻って休憩を取るように言った筈だけど」
そう。
うっかり作業中にぼおっとしてしまっていたことを見つかって、体調管理も碌に出来ないのだから仕事なんてしてもミスをするだけだろう等々くどくどと説教をされながらも自室に追いやられたのが2時間帯は前の出来事だった。
この大きなダイヤの城はどこへいってもやることに溢れていて、1日という区切りが無い世界だから尚更、キリのいいところまで作業を終わらせたいと没頭していたらちょっと寝るのを忘れてしまっていたのだ。
夜の時間帯があまり来なかったせいもある。
よりによってジドニーが見回っている時にやらかしてしまうなんて。
「でも、この資料があれば・・」
あと少しで資料が上手くまとめられそうだった。
シドニーに取り上げられてしまった分厚い資料を見れば、必要な数字が分かるはずで。
「そうしたら、あなたの仕事がもっと効率よく出来そうだったの」
「・・・・・」
いつもいつもシドニーの執務室で黒い引き出しの群れと戦っていて、どこにどんな資料が入っているかはもうだいたい頭に入ってきている。
渡された書類に目を走らせた時点で、これはあの時みたあの書類があれば・・と検討が付けられるものも増えてきた。
シドニーの指示を仰ぐ前に該当する引き出しを当てられた瞬間、シドニーも声を止めてこちらを見たのが分かった。
こみ上げる高揚感。
シドニーは、一呼吸置いてからまた何事も無かったかのように次の指示を出していたけれど、その時の作業はひと段落つくまでがあっという間だったように感じる。
休憩にしよう、と紅茶を入れてくれた瞳に、確かな何かを見たような気がしたのだ。
例えばそれは信頼というような、成長を認められたような。
だからつい、嬉しくなって・・張り切り過ぎてしまった。
「そんなことは望んでなんかいない」
「・・・シドニー」
ため息を吐いて逸らされた視線に思った以上にショックを受けた。
それがまるで落胆されたかのようで、確かに空回りをしてしまったかもしれないがそんなこと初めから望んでいない、無意味だと言われたように感じてしまった。
書庫の奥、暗がりの中で重たい沈黙が広がっていく。
でも、そうだ。
資料をまとめたいと思ったのは自分で、それは自分で勝手にやり始めたことだ。
仮に彼の仕事が捗るようにと思ったとしても、頼まれてもいない自己満足のこと。
そのせいで普段の仕事に支障が出るようなら意味が無い、ただの我がままだった。
「ごめんなさい」
項垂れた視界に自分の赤い靴の爪先とそこに被さるようなシドニーの垂れた耳の影が重なる。
失望、させただろうか。
もう手伝わせてくれなくなる?
知らず拳を握り俯く後頭部に、何かがそっと触れた。
「それじゃあ足りない」
「・・・?」
「部屋に、戻って」
短く告げられた声、ふいと踵を返す背中を見る。
髪を、撫でられたように感じたけれど微か過ぎて分からなかった。
勘違いかもしれない。
「何をしてるの?聞こえなかった?」
少し歩いてから、こちらが歩き出さないのにじれたようなシドニーに急き立てられるようにして、早足で書庫を出る。
扉を軽く抑えてているシドニーの脇を通り過ぎる。
パタンと扉を閉じたシドニーはまた、自分を追い越して歩いて行った。
片手に重たい資料を持ったまま。
行く先は・・どうやら私の部屋まで着いてくるつもりのようだ。
仕事はひと段落したのだろうか。
思ってからふるふると首を振る。
彼がいつもこなす仕事量からいって終わったとは到底考えにくい。
自分の様子を見に来たのだろうか。
・・・心配、させたのだろうか。
「・・リス、アリス!」
「あ・・、ごめんなさ・・!」
急に大きな声をかけられてビックリして顔を上げれば、間近にこちらを覗き込むオッドアイと目が合った。
「・・・もういい」
「!」
くっときつく目を細めてこちらを向いて言いきられた言葉に、衝撃を受ける。
今度こそ、見捨てられた・・・?
「シ、ドニー・・っ?!」
怒ったように低く言い放ったと思えば、その体がすっと視界を下がる。
何事かと思う間もなくスルリと背中と膝裏に腕が回されて、視界がガクンと揺れた。
「ちょ、待ってシドニー、大丈夫よ歩けるわ」
「君の大丈夫は全く信用がならない。・・持って」
耳元で言われた言葉に反射的にその手の先にある資料を受け取って腕に抱えてしまう。
そこから先は無言で歩き出したシドニーによって、自室のベッドまで搬送されることになった。
「いつか、いなくなるくせに」
無理やり寝かしつけられたベッドの上から不機嫌そうな、言い捨てるような声が降ってくる。
被せられた毛布を少し下げて下から見上げれば、切羽詰まったように歪む赤と黒の双眸が見えた。
「こんなことで倒れるくらいなら、もう」
「お願い、その先は言わないで」
もう、手伝わなくていい、そう言われるような気がした。
普段から、君がいなくても一人でも出来るし今までもそうしてきた、と幾度となく言われてきたからおそらくは間違いない。
「シドニー、お願い」
仕事を任されなくなったら、私はここでただのお客様だ。
客は、いつかいなくなるもの。
「私、ここにいたいの」
「っ・・・」
眉根を寄せるその顔を手を伸ばしてそっと撫でる。
いなくなるくせに、と言ったシドニーの言葉にそんなことは無いとは返せなかった。
自分という存在はそういうものだと、度重なる引っ越しを経験して分かったこと。
でも、「そうだ」ともはっきり返したくなかった。
「今、私はここにいるし、ここにいたいと思っているわ」
信じてもらおうとは思っていない。
でも、伝えたかった。
捨てられることに怯えて、他人の手を取れない孤独な黒うさぎ。
それでも仕事をくれた。
ここに居ていい理由をくれた。
その手に、ただ返したいのだ。
「・・信じられない」
そういうと分かっていた。
その泣きそうな顔に微笑み返す。
「信じなくてもいいわ。その代り、私に仕事をちょうだい」
ここにいるために。
「出来るだけ、あなたの傍にいたいの」
そう言って笑えば、暫くしてシドニーの眉は少し下がった。
「その言葉も、信じられない」
言って、屈みこむようにこちらを包み込む、そのビロードのように綺麗な黒い耳に頬を寄せる。
ふわふわとしてとても気持ちが良い。
デスクワーク派だけどしっかりとしている腕に抱かれてほっとする。
「だから私から傍にいくようにする」
ぎゅっと強く抱きしめられて、そして少し離れて顔が見える距離になる。
囁くようにいって、そして静かに唇が重なった。
◆◇*------------*◇◆
illust by Blancma
background by *ヒバナ * *